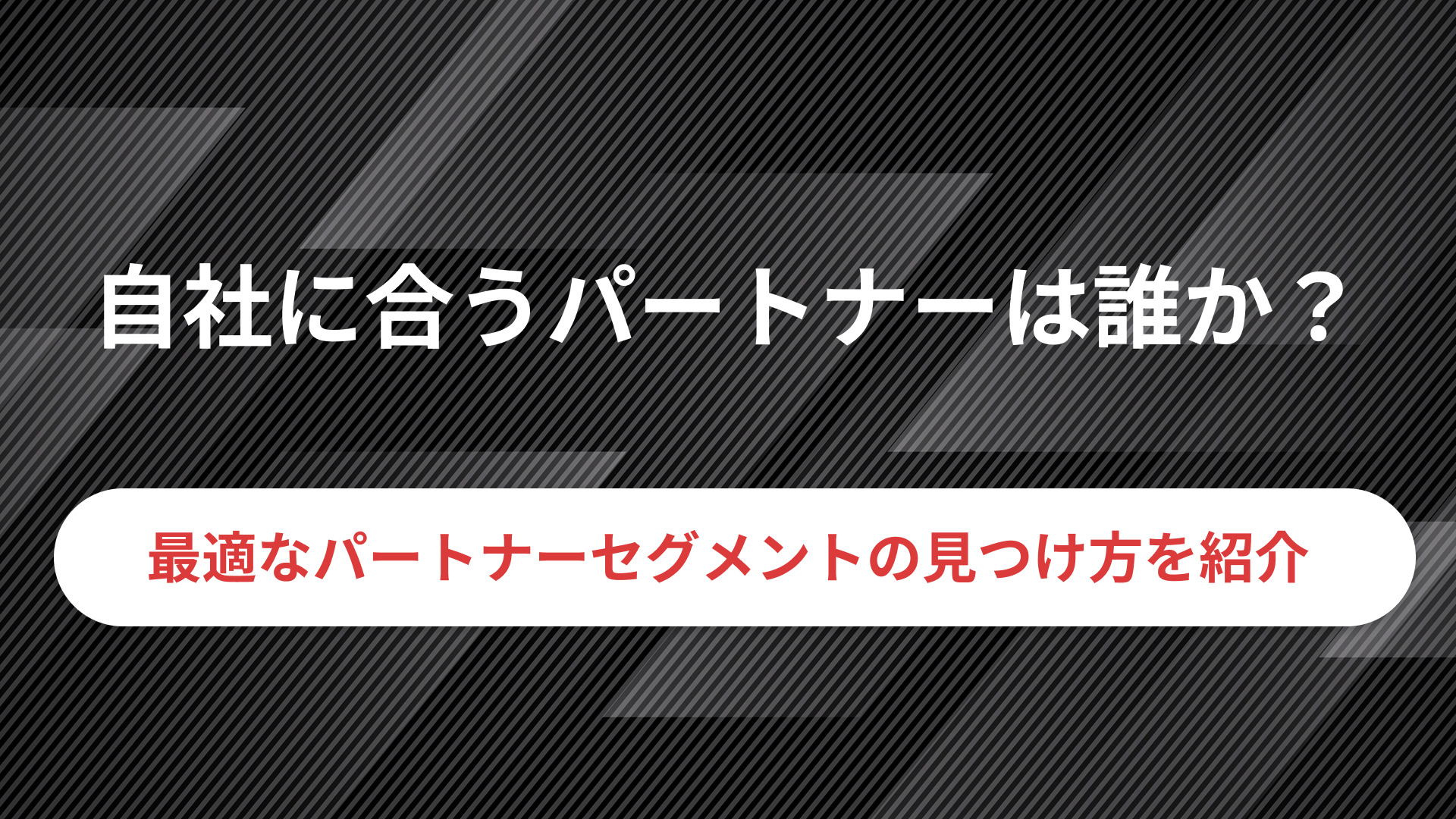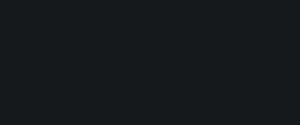目次
パートナービジネスを展開するにあたって、「どのようなタイプの企業と組むべきか」が明確になっていないまま開拓を進めてしまうケースは少なくありません。これは、パートナー開拓の前段階であるターゲットパートナー像の定義が不十分であることに起因します。戦略が不十分なままパートナー開拓を行うと、パートナーの稼働率が上がらず、パートナービジネスが停滞しやすくなります。
本来、パートナー開拓は「誰にアプローチするか」を戦略的に決定するところから始まります。商材の特性や顧客層との相性、営業手法の親和性などを踏まえて、自社にとって効果的なパートナーのタイプを見極めることが、パートナービジネス全体の成果を大きく左右します。
本記事では、自社にとって最適なパートナー像を戦略的に定めるために必要な、基本的な考え方と具体的な手順を整理します。
そもそもどのようなタイプのパートナーが存在するのか?
自社に最適なパートナーセグメントを見極めるにあたって、どのようなタイプの企業が存在し、その中でも自社にとって最適な企業タイプはどれなのかを把握しておく必要があります。ここでは、主なパートナータイプの特徴と、協業の可能性を見極めるポイントを整理します。
■ SIer
顧客に応じたシステム開発・保守を行う業態で、規模により協業の難易度が異なります。
- 大規模SIerやその子会社は、単価の高い案件を主力とし、SaaSとの親和性は低めです。ただし、ITトレンドに合致した商材であれば、関心を示す場合もあります。
- 中小SIerは、既存顧客に密着した営業を行っており、商材と既存顧客との相性次第では協業の可能性があります。
■ 流通系ディストリビューターと傘下代理店
広範な販路を持つディストリビューターは、全国の販売代理店を束ねており、SaaS商材の流通における中核的存在です。契約によって広範な展開が可能になります。
その傘下の二次代理店は、主に中小企業に提案活動を行っており、自社商材と親和性の高い部署に強みを持つ代理店を選定することが重要です。
■ 地方を地盤とするパートナー
- 地方銀行は、経営支援の観点から財務・業務系SaaSと高い相性を持ちます。
- 地場SIerは中堅・中小企業との関係性を持ち、導入先が自社商材と合えば協業可能性があります。
- 商工会・商工会議所は、中小企業向けに有用なテーマであれば、紹介や共催施策などの連携が見込めます。
■ キャリア系・事務機系販社
- キャリア系(通信会社の販売代理)は、スマートフォンや回線契約と連動した勤怠管理などのSaaSと相性が良好です。
- 事務機系販社は、中堅・中小企業向けの総務・バックオフィス商材に強く、一次代理店としての活用も可能です。
■ 営業代行業者・販売代理専門企業
ディストリビューター傘下ではない独立系代理店も存在し、独自の顧客網を持つケースがあります。ただし、活動の持続性や営業品質にはばらつきがあるため、事前の実績確認が不可欠です。
■ コンサルティングファーム・専門士業
販売代理とは異なりますが、業務改善や導入助言の文脈で提携可能なケースがあります。経営・業務系コンサルや会計事務所などは、業務SaaSとの親和性が高い領域です。

ターゲットとなるパートナーセグメントの定め方
次に、自社にとって最適なセグメントを見極めるための基本的な2ステップを紹介します。
1. 自社製品の特徴の棚卸し
まず、自社の主要顧客像を整理します。具体的には、業種(例:製造、医療、建設)、部署・役職(例:経理部門、総務部門、経営層)、企業規模(例:従業員数・売上規模)の観点で顧客情報を分類します。この顧客情報の整理結果は、次章で紹介するパートナーターゲティングの判断材料となります。
また、これらの情報をもとに、主要顧客が日常的に利用している製品カテゴリや、どの部門・役職が意思決定に関わっているかを把握します。 たとえば、経理部門が主な利用部門であれば、会計管理や経費精算といった領域の製品が導入されていることが多く、それらの製品がどのような流通経路で販売されているかを理解することが、次のステップでパートナー候補を絞り込む際の材料になります。
2. 組むべきパートナーセグメントの見極め
まずは、公開情報(企業Webサイト、製品紹介、販路情報など)を活用して、自社の製品が市場でどのような経路を通じて流通しているかを把握します。どのようなタイプのパートナーが商流の中で登場しているか、どの企業が顧客にリーチしているかを観察することで、協業可能性のあるパートナータイプを浮かび上がらせることができます。
そのうえで、どのタイプのパートナーと組むべきかを、次の3つの判断軸から検討します。
(1)主要顧客の属性重複
自社の主要顧客層と、パートナーが普段接している顧客層が一致しているかを確認します。たとえば、自社が中堅製造業の現場部門に強い場合、同じ属性をカバーする販社は有力候補となります。
レバレジーズ株式会社のパートナーセールスに携わる徳間氏は、パートナー開拓の際に最も重視していたのは、「自社の主要顧客が属する業界から逆算し、その顧客と繋がりのある企業をパートナー候補として洗い出すこと」だったと語ります。顧客業界を分析し、その業界内でどのような商流が存在しているかを把握することで、直接の取引先となり得る企業群が浮かび上がるほか、たとえば労務関連のように、商流とは異なる接点を持つ企業も候補として捉えることができたといいます。

(2)営業手法や単価との親和性
自社の営業スタイルと、パートナーの営業手法が適合しているかを確認します。たとえば、トップダウン型で経営層から提案を進める場合、経営層との接点がある代理店であることが望まれます。また、製品単価が高い場合は、商材単価が近い代理店との相性が良く、取り扱いに前向きになりやすい傾向があります。
(3)組みやすさ(パートナーの規模)
パートナーの規模も考慮します。大規模代理店は取り扱い商材が多く、競合も多いため、自社製品が埋もれるリスクがあります。一方、パートナーの規模が自社の支援体制とバランスしていれば、優先度を上げてもらいやすく、販売活動の立ち上がりも早くなります。

セグメントは一つに絞る必要はない
上記の判断軸をもとに、自社にとって最も効果的なパートナータイプを複数セグメントで定義することも可能です。たとえば、中堅・中小企業向けバックオフィス特化の事務機販社と、地域密着型の金融機関を併存させることもあります。重要なのは、分類ごとに戦略と施策が明確になっていることです。
「共創ベネフィット」のある協業関係を目指す
パートナーセグメントを定義した後は、それぞれのセグメントに対して、どのような協業関係を築くかを設計していく必要があります。その際の出発点となるのが、「共創ベネフィット」の可視化です。
共創ベネフィットとは何か?
共創ベネフィットとは、協業によってパートナーの本業にプラスの影響がある状態を指します。言い換えれば、「この商材を取り扱うことで、パートナー自身の収益や顧客提供価値が高まる」という構造が成立している状態です。
たとえば、会計管理クラウドと会計事務所の関係は、典型的な共創ベネフィットの例です。会計事務所は、会計ソフトを活用することでクライアントへの業務効率化支援が可能になり、「DXに対応した事務所」としての競争力を高めることができます。さらに、クラウドサービス提供企業からの顧客紹介や提携によって、自らの集客にもつなげることができます。こうした関係性は、ベンダー・パートナー双方にとって、明確なメリットが存在します。
なぜ共創ベネフィットが必要なのか?
パートナーにとって、協業の判断基準は、売れるかどうかだけではありません。営業リソースには限りがある中で、自社の事業とどれだけ親和性があるか、将来的な収益や顧客関係の強化につながるかといった観点が重要になります。共創ベネフィットが不在の提案は、代理店から見れば「一方的なお願い」に映り、優先度が低くなる傾向があります。
パートナーセグメントを定めた後は、「なぜそのセグメントと組むのか」「どのように相互メリットを作れるのか」を具体的に検討する必要があります。共創ベネフィットは、パートナー施策の核となる設計思想であり、協業を継続的に成長させるうえで不可欠な要素です。
共創ベネフィットの考え方・つくり方
共創ベネフィットを設計する際には、以下のような視点から整理すると効果的です。
まず、パートナーの本業を起点に考えることが重要です。たとえば、地方銀行は企業向け融資や経営支援を通じて地元企業と強固な関係を築いています。このような銀行に対しては、経理業務の可視化や資金繰りの予測など、経営支援に直結するSaaSを提案することで、銀行本体の提供価値を高めることができます。
次に、パートナーの顧客に提供できる新たな価値を見出す視点も必要です。たとえば、複合機やビジネスフォンを扱う事務機販社は、総務部門と継続的な接点を持っています。このような販社に対して、ワークフロー管理や勤怠管理といったバックオフィス向けSaaSを提案することで、顧客との関係性を深めるための新たな切り口を提供できます。
また、共創ベネフィットは金銭的インセンティブだけでは成立しません。営業担当が「話のネタとして使いやすい」「競合との差別化になる」と感じられるようなメリットの設計も重要です。たとえば、「この商材を扱えば他社より先進的な提案ができる」といった要素があれば、営業現場での提案優先度が上がります。
セグメントに基づいたパートナー候補のリストアップ
最後に、定めた理想的なパートナーセグメントから、実際にアプローチすべき企業の候補リストを作成する手順を紹介します。
まずは、信頼できる複数のデータソースを横断的に活用し、該当セグメントに属する企業を広く洗い出します。具体的には、SalesMarkerのようなリスト作成ツールに加え、業界団体の会員名簿、商工会議所の企業データベースなどを併用し、リストの網羅性を担保します。
次に、従業員規模、商流の特徴、自社とターゲット市場の重なり度合いなどの観点でフィルタリングを行い、候補を本命と育成枠に分類します。重複企業は早期に除外し、過去の接点や取引実績がある企業にはその情報を追記しておくことで、効率的な開拓が可能になります。
また、リストアップした後の活用フェーズでは、PRMなどのツールを活用して面談結果や担当者の温度感を一元管理し、開拓状況に応じた優先度の自動更新を可能にします。リストは正式稼働前に関係部門とレビューを行い、優先度と担当の合意形成を経て運用を開始します。
運用開始後は、週次で更新履歴を残しながら、有望な新規候補を随時追加・整理していくことで、リストを常にアクティブな状態に保つことができます。
まとめ:セグメントの定義はパートナービジネスの起点
パートナービジネスの成否は、どのパートナーと組むかで大きく変わります。ただ契約数を増やすのではなく、「誰となら売れるか」「どこなら共に市場を広げられるか」という視点で、ターゲットとなるセグメントを見極めることが重要です。
そのためにはまず、自社の顧客像・営業スタイル・商流を棚卸し、どのようなタイプのパートナーが自社と親和性を持つのかを具体化しておく必要があります。定めたセグメントに対しては、「共創ベネフィット」を設計し、相互にメリットのある関係性を築く準備を整えましょう。
また、セグメント設計は一度で正解にたどり着くものではありません。実際にアプローチや協業を進める中で、仮説を検証し、必要に応じて軌道修正することが成果につながります。セグメント設計と実行・検証はセットで考えるべきプロセスです。