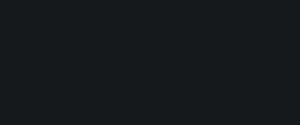目次
オールインハウスでサービスを展開してきた株式会社レバレジーズですが、外国人の採用支援サービスにおいてパートナービジネスに着手されています。開始からわずか1.5ヶ月と、凄まじいスピードでパートナービジネスの立ち上げを進めています。今回は、レバレジーズでパートナービジネスを推進する徳間様に、「パートナービジネスの重要性とパートナー開拓」についてお話を伺いました。
地方では“紹介文化”の壁、IS架電が刺さらない
ーまずは貴社のサービスについてお聞きしてもよろしいでしょうか。
当社は外国人材の人材サービスを主軸としております。各種在留資格に対応し、現在は4つの商材を取り扱っています。企業ごとに最適な雇用形態や在留資格を設計・提案するサービスを提供しています。
ー德間様はパートナーのご経験がないと仰っていたと思いますが、前の部署での業務等をお聞きしてもよろしいでしょうか。
元々所属していたのは技能実習チームでして、メインの業務として、既存顧客へのフォロー業務とリピート営業、また時間のある時には新規営業(テレアポ)を行っておりました。
ーなるほど。ありがとうございます。パートナービジネスを始める前の貴社ではどのような施策をしていたのでしょうか。
施策は大きく2つありました。
1つ目にマーケティング施策として、広告出稿やInstagramなどのSNSを活用し、リード獲得に取り組みました。2つ目に営業担当の施策として、担当者によるオンラインセミナーの定期開催に加え、DMや手紙でのアプローチを実施しました。いずれもマーケティング部門主導というより、営業部自ら運用するケースが多かったですね。
ーありがとうございます。直販での営業を推進する中で、課題はありましたでしょうか。
直販を推進する中で、課題は大きく二つありました。
1つ目は、地方企業へのIS(インサイドセールス)による架電がほとんど効果を発揮しなかった点です。地方には企業同士で紹介し合う“紹介文化”が根強く、アポを獲得したとしても、検討段階にいくことが少なかったり、商談後連絡が取れなくなったりということがありました。
2つ目は、人員の変動が施策に与える影響です。海外事業部の拡大に伴い、退職・部署異動・新卒入社が重なり、直販施策が属人化していたため、担当者が替わると施策自体が止まってしまう場面がありました。
直販が届きにくい規模へのアプローチ手段としてパートナービジネスを導入
ーなるほど。直販でそのような課題がある中で、貴社がパートナービジネスに取り組み始めた理由をお聞きしてもよろしいでしょうか。
直販ではアプローチが難しい規模の企業にリーチしたかったためです。10名前後の企業には直販で営業できていましたが、従業員約30名規模の企業には、前述の直販の課題があり、接点づくりが非常に困難でした。
当初はパートナービジネスの経験も知見もありませんでしたが、直販やマーケティングに代わる施策を検討する中でパートナービジネスを知り、弊社が狙いたい企業に届く手段になり得ると判断しました。その結果、パートナービジネスの導入を決めました。
ーなるほど。以上を踏まえ、貴社におけるパートナービジネスの位置付けや役割を教えてください。
弊社におけるパートナービジネスの位置付けは、新たな流入経路の拡張です。
自社のマーケティング施策(広告・SNS 等)や、営業部主導のセミナー、直販のIS(インサイドセールス)は継続しつつ、これらにもう一つの商談・受注チャネルを加える目的でパートナービジネスに取り組んでいます。既存チャネルを補完し、到達範囲を広げる“第二の入口”として機能させていきます。
ーなるほど。直販とパートナービジネスの“二軸”で進めることが重要ということですよね。
はい。どちらか一方に偏らず、直販とパートナービジネスの両方に取り組むことが重要だと考えています。
弊社は直販文化が強い一方で、直販以外の販路を拡張できれば、到達範囲が広がり、事業規模の拡大につながります。二軸化によって、リードや商談、受注の獲得ための新たな経路と成果の安定化を図っていきます。
ーなるほど。ありがとうございます。オールインハウスである貴社がなぜ今パートナービジネスに着手したのでしょうか。
安定的に成果を出すまでに時間がかかる施策だと考えたからです。
パートナー企業との関係構築や情報共有を重ね、紹介をいただくまでのリードタイムが長いため、着手を遅らせるほど成果の立ち上がりも後ろ倒しになります。であれば、早く始めて早く学び、早く成果を出す方が合理的だと判断しました。
また、パートナービジネスは立ち上がりこそ時間を要しますが、一度成果が出始めると再現性が高まり、積み上がる特性があります。将来の成長カーブを見据え、早期着手が最善だと考えました。
ーなるほど。ありがとうございます。

パートナープログラムや説明資料の座組みを整えたら、即パートナー開拓
ー実際に1.5ヶ月で立ち上げたとのことで、パートナービジネスに着手するにあたり、最初に取り組んだことをお聞きしてもよろしいでしょうか。
最初に着手したのは、パートナープログラムとインセンティブ設計などの“座組み”づくりです。インセンティブは土台となるため、時間をかけすぎず、しかし丁寧に要件を固めました。同時に、パートナー企業向けの説明資料一式を新規作成しました。プログラムとインセンティブを確定後は、すぐに開拓フェーズへ移行し、立ち上げスピードを意識しながら弊社と親和性の高いパートナー探しを進めました。

ーなるほど。パートナー開拓の手法について、具体的にお聞きしてもよろしいでしょうか。
弊社は主に企業のWebサイトの問い合わせフォームからパートナー提携の打診を行っています。フォーム経由でご返信をいただいた後、オンライン/対面で詳細をご説明する流れです。パートナー担当や協業担当の方には代表電話ではつながりにくいことが多く、テレアポは有効性が低いと判断しました。そのため、フォームで要件を簡潔に伝えるアプローチを継続しています。
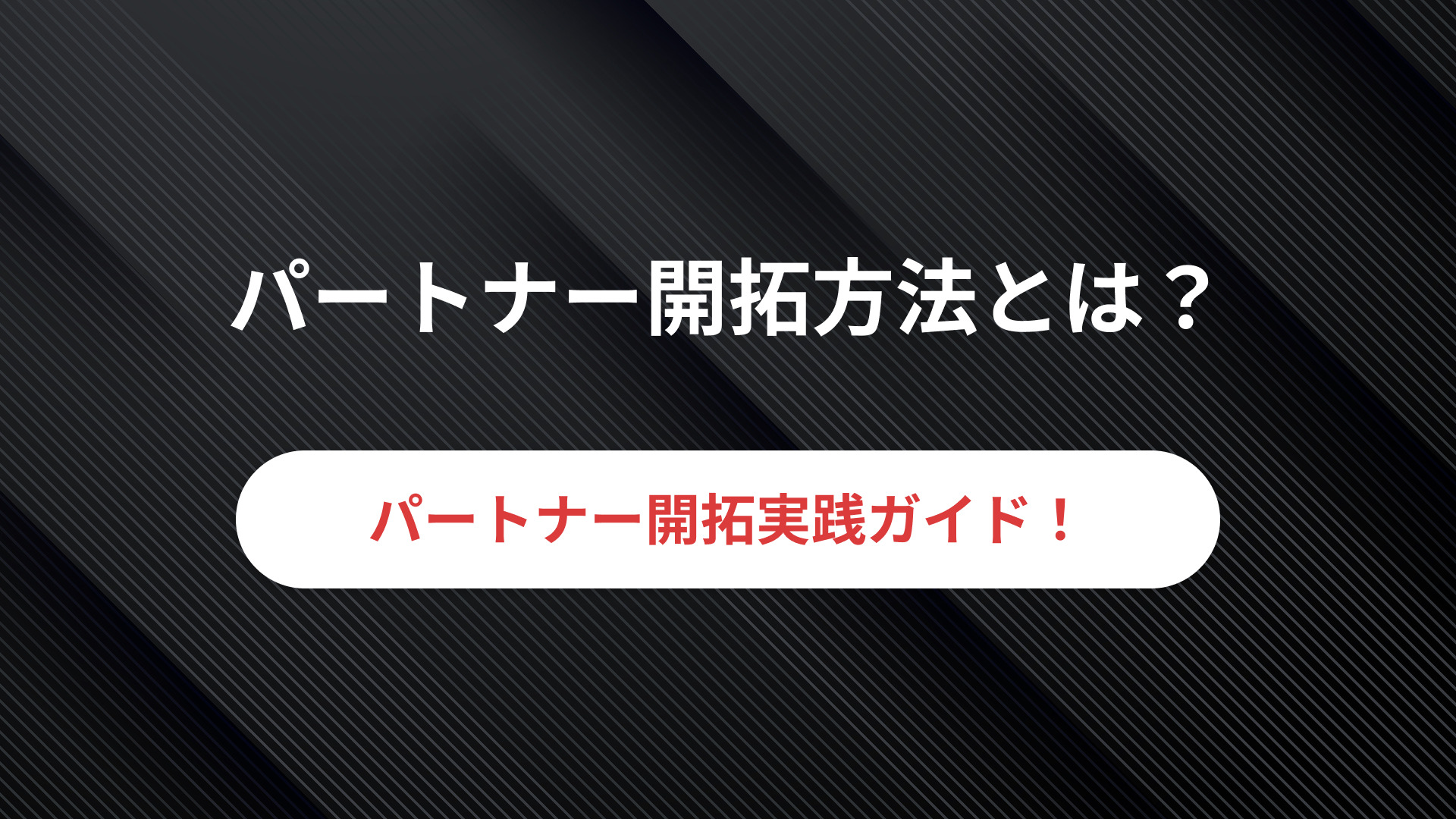
ーなるほど。その点からテレアポより問い合わせフォームを重視しているのですね。
そうですね。最初は、テレアポと問い合わせフォームは一緒には行っていたのですが、代表電話かコールセンターで止まってしまうのが非常に多かったです。また、 問い合わせフォームからの反応が意外とよかったため、テレアポではなく問い合わせフォームから問い合わせています。
ーなるほど。そのほか、開拓時に有効だったアプローチはありますでしょうか。
はい、社内連携によるリード共有が非常に効果的でしたね。
他部署のメンバーが参加した業界イベントやセミナーから、パートナー候補の企業リストを共有してもらい、優先度を付けて順次アプローチしました。部署横断で情報を集めることで、見落としていた候補の発掘や、初回接点までのリードタイム短縮につながったと感じています。個人的にも、社内連携を通じてパートナー候補を見つけることは、再現性の高い有効な手段だと思います。
“逆算思考”で、思い浮かばない業界のパートナー候補が増える
ーさらに読者がイメージしやすいよう、パートナー開拓で心がけていたことをお聞きしてもよろしいでしょうか。
最も重視していたのはターゲティングです。パートナー企業のビジネスモデルが弊社(海外人材)と噛み合うかをまず確認しました。そこから最終顧客から逆算し、「この会社はおそらく誰と取引があるか/どことつながっていそうか」を仮説立てして当たりにいきます。
たとえば建設領域で最終的に工務店へ人材を届けたい場合、商流の上流(ゼネコン)にパートナー打診を行います。建材事業者や労務系企業も同様の方法で開拓を行いました。
この“逆算思考”で進めると、当初はパートナー像が浮かばなかった企業でも十分に候補になりうることが分かりました。商流を丁寧にたどることで、業界を限定せずにパートナー候補を広げられると感じています。
ーありがとうございます。仮に候補が多く出た場合、どのような基準で優先順位を付けるのでしょうか。
判断軸はサービスの親和性です。具体的には、相手が無形商材/有形商材のいずれを主に扱うかを見ます。
弊社は無形(サービス)ですので、無形×無形は相性が高い一方、相手が有形中心の場合は“合わせ技”(有形+当社サービス)で商談価値を高められるかを提案します。
また、初回面談では前提知識の有無を早めに確認し、今後の進め方(役割分担・想定ユースケース・初回案件の作り方)を合意形成をします。親和性を軸に据えることで、この合意形成もスムーズに進み、以降の開拓効率が上がりました。
ー詳細にお話いただきありがとうございます。

売りにくさの正体は“メリットの言語化不足”
ー実際にパートナービジネスに取り組む中で、難しいと感じた点をお聞きしてもよろしいでしょうか。
開拓を進めるほど、金額以外のメリットを伝え切る難しさと、その重要性を強く実感しています。
当初は価格の説明に比重が寄っていましたが、当社のサービス×パートナー企業のサービスを組み合わせたときに、顧客へどのような価値(成果・効率化・収益性)が生まれるのかを具体的なユースケースと数値感で示せない限り、パートナーは「売りにくい」と感じてしまいます。
そのため面談では、導入後の効果まで踏み込み、パートナーが顧客に語れる“価値の言語化”を徹底しています。ここを丁寧に設計・共有することが、パートナービジネス特有の難所だと考えています。
ーなるほど。確かにそうですよね。
また、私がもう一つ重視しているのが、ビジョンや目標の一致です。パートナー候補各社のホームページに記載されたミッション/ビジョンなどの目標を確認し、弊社の掲げる「人材不足の解消」と同じ山を登れるかを見極めます。
目標が一致している企業は、初回説明の段階から定性的な価値(社会課題の解決・顧客体験の向上等)を共有しやすく、以降の連携もスムーズです。結果として、パートナー側も“売りやすい”と感じやすい。この共通の目的意識を明確に言語化して伝えることで、金額に依存しない提案の説得力が高まり、商談の前進につながると考えています。
ーありがとうございます。
コントロールの外で進む――間接販売ならではの難易度
ー德間さんのご経験を踏まえ、パートナービジネスとの具体的な違いや難しさをお聞きしてもよろしいでしょうか。
パートナーセールスは、直販と異なり自社のコントロール外で状況が進む点が難しいと感じています。
一方で、パートナービジネスは一定の状態まで立ち上がると、自律的に成果が積み上がる特性があります。ただし初期は、パートナーとの密なコミュニケーションや役割分担の明確化など、やるべきことが多く、伴走が不可欠です。
直販はタイミングや運要素の影響が大きいため、テレアポや展示会で商談・受注が増えても、安定的な成果、再現性を出すのは難しい側面があります。パートナーは仕組みで安定化させる発想、直販は瞬発力という違いだと捉えています。
レバレジーズの実践:机上調査より“会って話す”が効く理由
ー直販を経験された德間さんだからこその意見だと思います。以上を踏まえ、読者が実務に生かせる学びやヒントを教えてください。
まず、「想定外の業界=候補外」ではないと考えることです。パートナー開拓では、「うちの商材を売れるか分からない」「ターゲットが見えない」と迷う局面が少なくありませんが、まずは担当者と対話し、最終顧客や提供価値の重なりを一緒に探ることが有効です。
次に、イベントでの現場対話を重視します。机上の調査だけでなく、会場で話すと「最終的な顧客層は同じだった」という発見が生まれ、行動ベースの次アクションが定まりやすくなります。リード獲得に限らず、仮説検証と関係構築の面でも効果的です。
ーありがとうございます。

今後の展望:パートナー母数拡大とパートナーセールスの認知拡大
ー今後の展望についてお聞かせください。
短期的には、今年中にパートナー契約50件の獲得を目標にしています。まずはパートナー母数の拡大をKPIとし、来期以降にアクティブ率や稼働度を評価指標として本格的にモニタリングする予定です。
長期的には、直販文化が強い弊社において、パートナービジネスを社内へ浸透させ、他部署や他事業部へも展開できる基盤を整えたいと考えています。これにより、全社目標への貢献度を高めていきます。
ー直販を経験された德間様はオールインハウスの貴社とパートナービジネスはどのように違うとお考えでしょうか。
事業を成長させる上では、オールインハウスの直販とパートナーセールス、この二軸を両立させることが極めて重要だと考えます。
直販は、顧客の声を直接吸い上げ、製品やサービスに迅速に反映できる点や、自社の戦略通りにビジネスを進められるコントロールのしやすさが大きなメリットです。その一方で、成果が営業担当者個人のスキルに依存してしまったり、人員の変動が売上に直結したりと、事業が不安定になる可能性を常に抱えています。
この課題はパートナーセールスによって解消できます。パートナーが持つ販売網を活用することで、直販だけではリーチできなかった顧客層にもアプローチでき、売上の安定化を図ることが可能です。しかし、その反面、顧客との関係が間接的になることで生のフィードバックが得にくくなったり、ブランドイメージの浸透や品質のコントロールが難しくなったりするというデメリットも存在します。
したがって、どちらか一方の手法に偏るのではなく、双方のメリットとデメリットを深く理解した上で、両チャネルを戦略的に両立させていくことが、持続的な成長には不可欠であると言えますね。
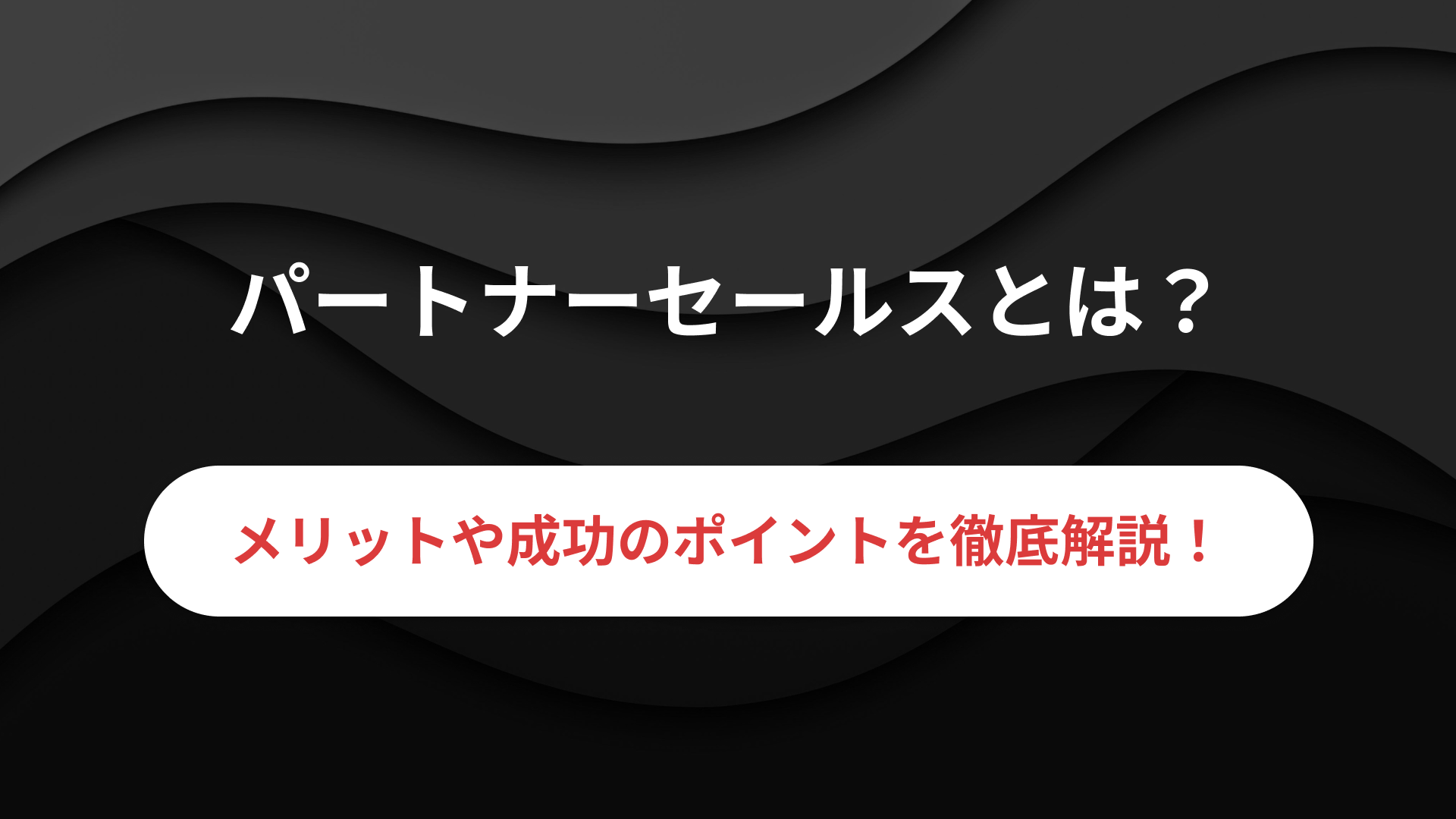
ーなるほど。最後にパートナービジネスにおける、德間様ご自身の目標もお聞きしてもよろしいでしょうか。
事業の拡大に加えて、パートナーセールスの社内認知を高めることが個人目標です。
そのために、パートナービジネスを直販・マーケティングに並ぶ主要な流入経路として位置付けられるよう、まずは成果を着実に可視化していきます。現状では、パートナービジネスの業務内容やビジネスモデルが十分に理解されていない面もあるため、成果・プロセス・成功事例を継続的に共有し、存在感の醸成につなげたいと考えています。
ー本日はありがとうございました。
【募集】レバレジーズ / 新規パートナー
レバレジーズ社のパートナーになりたい方は以下より問い合わせ
アドレス:narumi.tokuma@leverages.jp
レバレジーズ社サービスサイトは以下