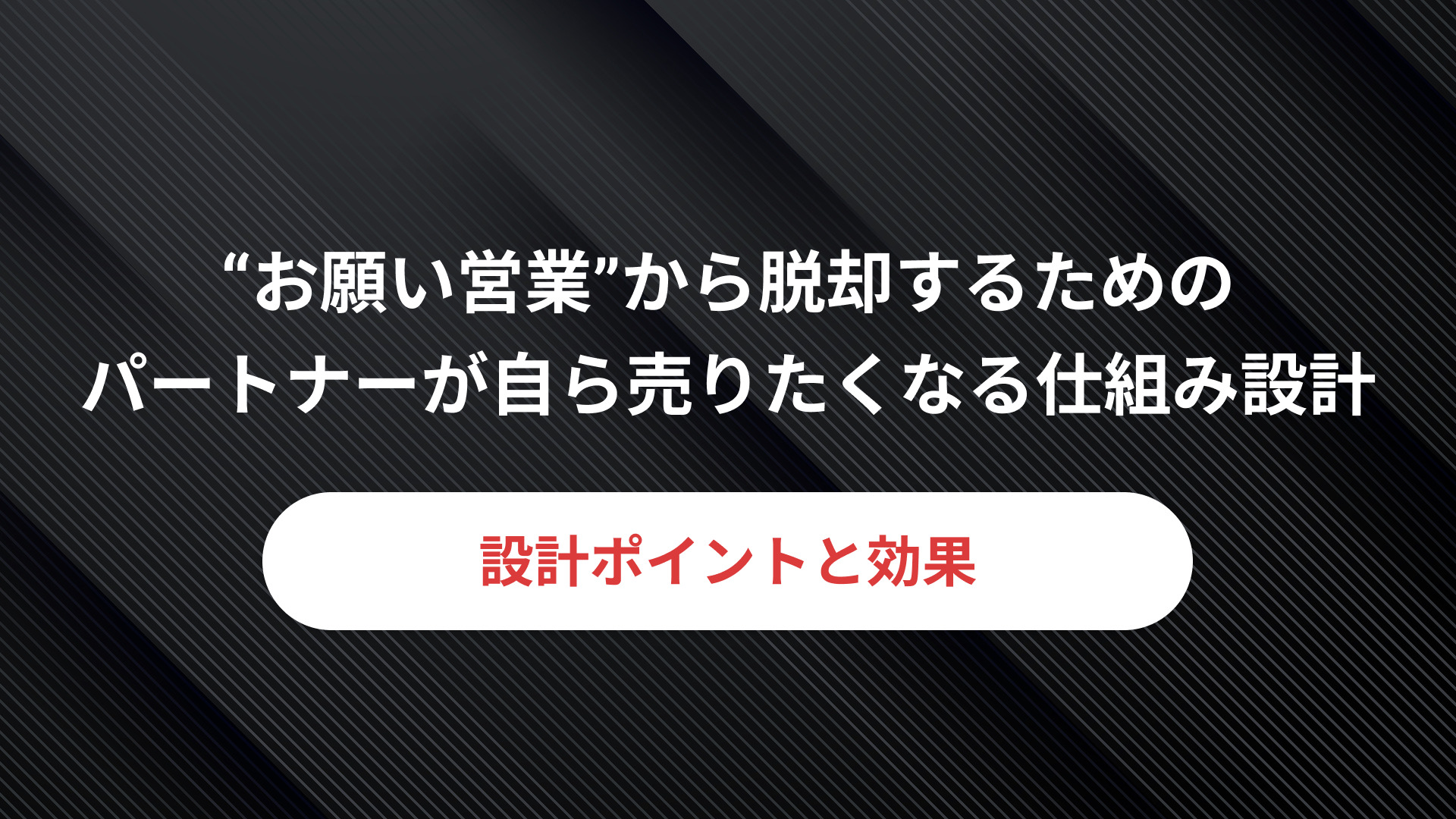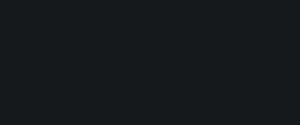目次
販路拡大のために契約したパートナー。しかし、思ったように商談が生まれず、やむなく自社側から「勉強会をさせてください」「何か案件ありませんか?」と声をかけ続ける——。これはまさに”お願いします営業”の典型的な構図です。
お願い営業の最大の問題点は、「頼み込むほど工数がかさむ」という悪循環にあります。しかも、お願いして動いてもらえたとしても、それは一時的な稼働に過ぎず、時間が経つとまたパートナーから案件がいただけなくなってしまいます。
このような”お願いします営業”の背景にあるのは、パートナーの状況が見えないことによる属人的な対応です。どこに課題があるかがわからないからこそ、ひたすらパートナーに”お願い”するしかないのです。
この状況を打破するには、属人化から脱却し、パートナーが自走するための仕組み=パートナープログラムを設計することが欠かせません。本稿では、「なぜパートナーが動かないのか」を3つのフェーズ(オンボーディング/アクティベーション/リテンション)に分けて整理し、継続的にパートナーが動き続ける状態を実現するための仕組みづくりのポイントを紹介します。
パートナーが動かないのは、どのフェーズの仕組みが弱いのか?
パートナービジネスを考えるうえで、「オンボーディング → アクティベーション→ リテンション」という3つのフェーズに分けて捉えることが重要です。
- オンボーディング:パートナーが製品や事業への理解を深め、活動準備が整うフェーズ
- アクティベーション:最初の商談・受注を通じて、パートナーが“稼働状態”になるフェーズ
- リテンション:活動を継続し、売上が安定する状態を維持するフェーズ

パートナーが動かないと感じるとき、その原因は必ずしもパートナーのやる気や意欲の問題ではありません。多くの場合、どこかのフェーズにおける仕組みの不備が原因で、特に稼働する必要がない状態になっているのです。
重要なのは、「このパートナーはなぜ稼働していただけないのか?」を感覚ではなく、フェーズごとの課題として切り分けて把握する視点です。
以下に、3つのフェーズごとに見られる典型的な「パートナーの動きが止まる原因」を整理します。
オンボーディング: 契約したものの、製品理解や営業準備が十分でなく、「誰にどう売ればいいのか」が見えずに最初の一歩を踏み出せない。
アクティベーション: 提案や商談の機会はあっても、「この商材は確かに売れる」という成功体験が得られず、商材を必要とする顧客像を思い描けないため活動が続かない。
リテンション: 一度は成果を出したものの、その後の支援や接点が不足し、商材提案の優先度が下がって協業が途切れてしまう。
パートナービジネスは、契約して終わりではなく、動き続けてもらう仕組みをどこまで設計できるかが鍵になります。
オンボーディングプログラム ― パートナーが最初の一歩を踏み出すために
パートナーがなかなか動かないと感じる背景には、パートナーが契約後も実際の営業活動に取り掛かることができていないという構造的な問題が潜んでいるケースが多くあります。
例えば「製品は理解したが、どの顧客にどんな切り口で提案すればいいのかが分からない」「最初のアプローチに必要な準備が重すぎる」といった状態です。これはパートナーの熱量や意欲の問題ではなく、動き出すための道筋が明確に示されていないことに起因します。
だからこそオンボーディングで必要なのは、単なる製品知識のインプットではなく、まず自社と組むことで得られるベネフィットを発見できるようにすること、そしてその達成に向けた具体的な目標を一緒に設定できることです。こうした仕組みが整うことで、パートナーは「この協業には意味がある」と実感し、自ら動き出せるようになります。
自社と組むベネフィットを示し、共通の目標をつくる
パートナーが最初の一歩を踏み出すには、単に製品情報を渡すだけでは不十分です。重要なのは、ベンダーとパートナーそれぞれの戦略をすり合わせ、この協業が双方にとって意味がある取り組みだと理解してもらうことです。
例えば、既存顧客に新たな価値を届けるという戦略を掲げるパートナーに対して、自社の商材とパートナーがすでに取り扱っている商材を組み合わせて顧客に提案することで、これまでとは異なる価値を顧客に提供できることを伝える。そうした説明によって、代理店契約がパートナー自身の戦略の実現に近づくのだと理解してもらうことが重要です。
レバレジーズ株式会社のパートナーセールスを担当する徳間氏も、共通の目的意識を明確に言語化してパートナーに伝えることが、社会課題の解決や顧客体験の向上といった定性的な価値の共有につながると話します。こうした価値が共有されることで、パートナー側は「売りやすい」と感じやすくなり、結果として金額に依存しない提案の説得力が高まるのだといいます。

こうした相互理解を踏まえた上で、契約初期に「共通の目標」を設定することも大切です。「今期は、貴社が強みを持つ◯◯業界において、◯件の導入を目指したい」といった具合に、数値や期間を伴う「共通の目標」をあらかじめ設定することで、協業の方向性が具体化され、パートナーにとっても取り組みが「自分ごと」になります。
共通の目標を持たない関係性は、“お願いします営業”に陥る温床です。「なぜ一緒にやるのか」「その結果、何を達成したいのか」をすり合わせる時間を、オンボーディング初期にしっかりと確保することが、長期的な自走につながる鍵になります。
成果報酬を前倒しで設計する
もう一つの障壁は、受注に至るまでパートナーに報酬やメリットが発生しないという代理店契約の構造にあります。つまり、どれだけ活動しても「受注」という成果が出るまでは何も得られないため、初動のモチベーションが生まれにくいのです。
これを乗り越えるには、受注前の行動にインセンティブを設計することが有効です。たとえば案件を登録した時点で報酬を支給したり、初回の商談にベンダーが同行した際にインセンティブを設けたり、最初の案件創出に対してキャンペーンを適用したりといった仕組みです。こうした仕組みがあれば、「動けばすぐに報われる」と感じてもらえるため、最初の稼働に対するハードルが下がります。
特に、まだ製品に慣れていない段階のパートナーにとっては、「まずやってみよう」と思えるかどうかが、商談のきっかけをつくり、受注へとつなげていけるかどうかを左右する分岐点になります。
スムーズに動ける導線を整備する
そして、最後の重要な要素が「動き出すための導線設計」です。
契約締結初期には、製品資料はどこにあるのか、提案書はどのように作るとよいのか、誰に質問すればよいのかなど、パートナーは様々な疑問を抱いています。そのため、こうした基本的な要素が整備されていないと、パートナーは一歩を踏み出すたびに不安やストレスを感じてしまいます。
具体的には、eラーニングや動画マニュアルによるインプット機会の提供、初回提案テンプレートやトークスクリプトの整備、案件登録や質問対応フローの明示といった仕組みが有効です。迷わず動ける状態=”導線が引かれた状態”を整えることが、オンボーディング成功のカギとなります。
オンボーディングは単なる準備フェーズではなく、パートナーが最初の成功体験を得るための重要な起点です。最初の一歩を踏み出せる環境を整えられれば、パートナーが主体的に動き続ける協業関係へと発展させることができます。
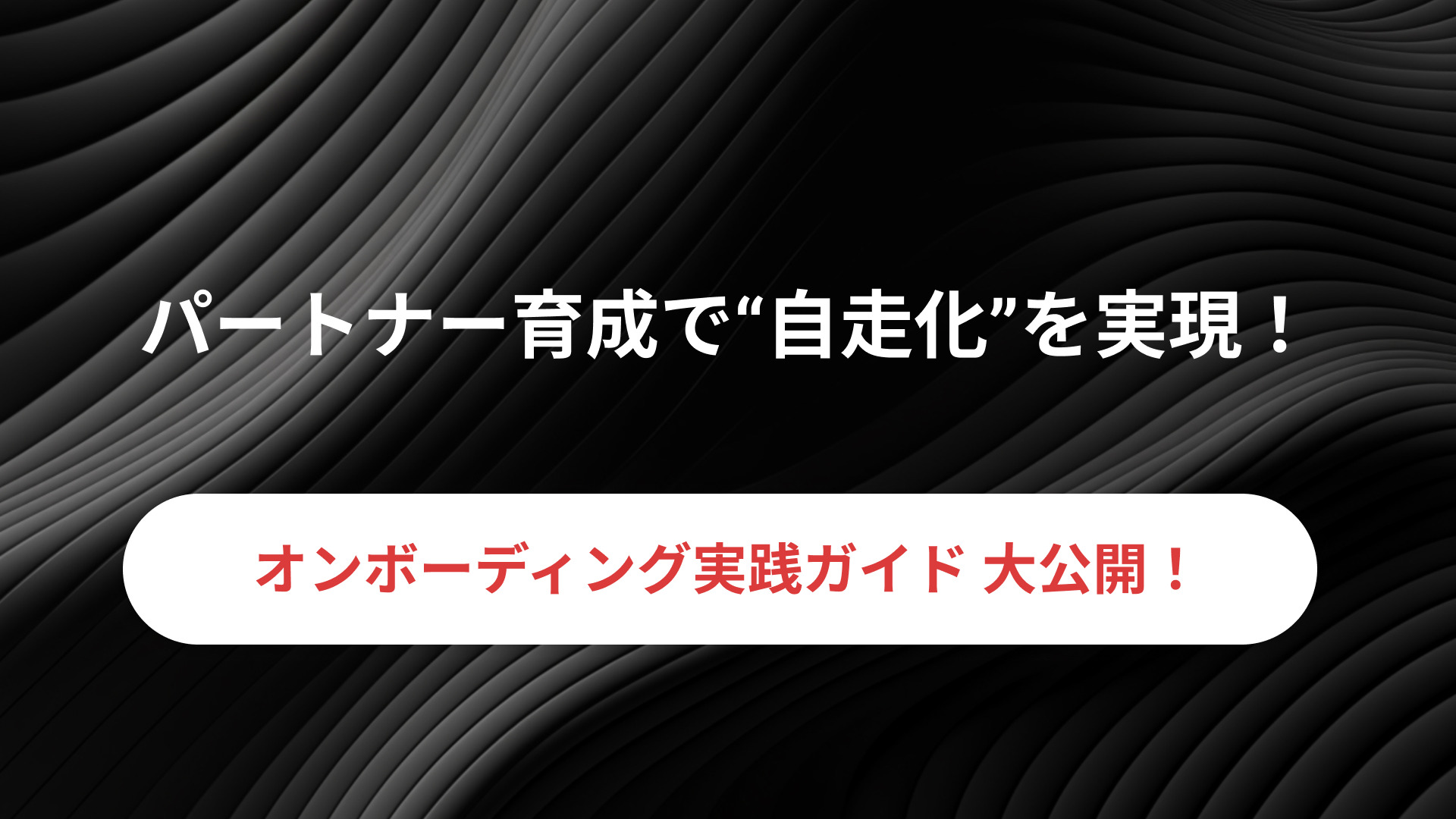
アクティベーションプログラム ― 動き始めたパートナーを成功体験に繋げる
パートナーとの協業がスタートしても、「結局、動いてくれなかった」というケースは少なくありません。これは、情報提供や意志のすり合わせだけでは、実際の営業活動に踏み出すハードルを越えられないためです。
パートナーが「売れるかもしれない」と思える状態から、「実際に売れた」という成功体験を得るまでの橋渡しこそが、アクティベーションフェーズの本質です。
最初は“伴走型”で支援し、成功体験を積ませる
どれだけ良い製品でも、初めて扱うパートナーにとっては「どう売ればいいのか分からない」「本当にニーズがあるのか不安」といった心理的ハードルが存在します。これを乗り越えるには、初期フェーズにおいてベンダーが積極的に伴走することが不可欠です。
具体的には、以下のような支援が有効です。
- ターゲットリストの提示:業種・企業規模・エリアなどに基づく優先アプローチ先の提案
- 商談資料やトークスクリプトの提供:初回提案時に自信を持てる支援キット
- 商談同行:ベンダーが1〜2件は実際に提案同行し、提案の型を共有する
- 初受注までのサポート設計:見積・契約・導入支援などの工程を明文化し、安心感を持たせる
これらの支援を行うことで、パートナーは「取り組めば成果が出る」というポジティブな成功体験を得て、自走への一歩を踏み出すのです。
キーマンを見つけて、アクティベートする
もう一つ重要なのは、“組織の誰をアクティベートするか”という視点です。稼働の可否は、パートナー企業の構造や体制に大きく左右されるため、「契約相手」だけでなく、現場で動く“キーマン”の特定と関係構築が鍵となります。
まずはパートナー企業の営業責任者や経営層と対話し、社内で旗振り役となれる人材を選定します。そのうえで、「3ヶ月で○件の商談を創出する」といった具体的な目標を共有し、役割とゴールを明確にします。
キーマン本人には、「この製品の専任担当として社内で存在感を高められる」「新しい領域に取り組む経験を積める」といったキャリア上の可能性やベネフィットを伝えることで、動機づけを強めます。あわせて、トークスクリプトや営業資料、商談同席といった支援も設計し、早期に成果を出せる環境を整備します。
成功体験が生まれたら、社内でその事例を横展開し、他メンバーの関心を引き出します。キーマンの育成は、単なる「一担当者の活躍」に留まらず、パートナー組織全体を活性化する起点となるのです。
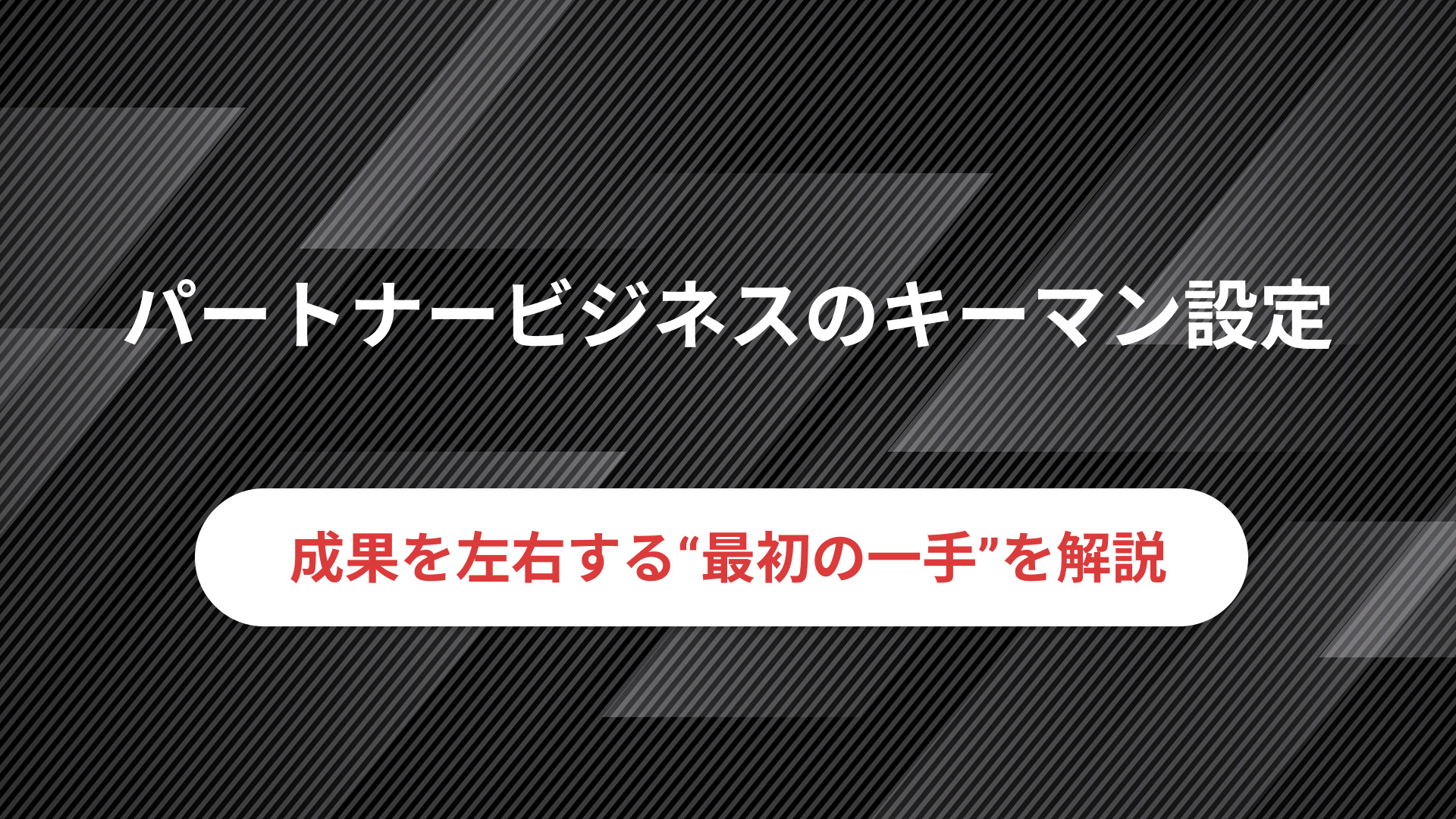
アクティベーションは、「自走のきっかけを生む」ための最重要フェーズです。パートナーが「やってみたら成果が出た」と感じるまで、もう一歩踏み込んだ支援と設計が求められます。
次章では、成功体験を積んだパートナーを継続稼働へと導くリテンション施策について、具体的に解説します。
リテンションプログラム ― 稼働パートナーを定着させる仕組み
初回の受注で終わらせず、継続的に成果を生み出してもらう仕組みをどう設計するか——それが「リテンション」のテーマです。
オンボーディングとアクティベーションで動き始めたパートナーも、定期的に接触しなければ自然とフェードアウトしてしまいます。接点を持つことで、モチベーションを安定させ、成果が上がる状態を習慣化することが重要です。そのために、次の3つのアプローチが効果を発揮します。
継続的な活動支援で“動き続ける”状態を維持
パートナーの定着には、継続的な情報提供と対話の仕組みが欠かせません。たとえば専用ポータルサイトで提案資料やニュースを一元管理することで、パートナーはいつでも自主的に情報収集が可能になります。
さらに、定例ミーティングやビジネスレビューを通じて、戦略のすり合わせや課題共有の場を設けましょう。たとえば、四半期ごとの活動レビューや案件進捗に応じた月次1on1など、パートナーの状況に応じて柔軟に設計することが重要です。
情報と対話の接点を絶やさないことで、パートナーの稼働率と満足度は自然と高まり、協業成果の最大化につながります。
ランク制度で「やればやるほど報われる」状態を設計する
「頑張った分だけ報われる」「次のステージがある」とパートナーに感じてもらうために、パートナーランク制度の設計は有効な手段です。
たとえば、紹介件数や成約件数に応じて、シルバー/ゴールド/プラチナといったランクを設け、上位パートナーには優先的な商談紹介・リード提供や特別単価や追加報酬の付与、月次相談の機会の提供といった特典を提供します。
例えば、HubSpotは、ソリューションパートナーに向けて「ゴールド/プラチナ/ダイヤモンド/エリート」の4段階のティア制度を導入しています。ランクは新規契約に基づく販売ポイントと、契約維持や活動支援を反映する管理ポイントで決まります。また、この到達基準を段階的に引き上げる仕組みも採用しています。Hubspotの国内トップパートナーである株式会社100の田村氏は、この仕組みにより、パートナーは常に新しいランクの基準を追いかけなければならないという思考になり、継続的な稼働へのモチベーションが強まるといいます。
このように「継続して動くほど、競合より優位になれる」という構造を作ることで、自然と継続稼働への意欲が高まる仕掛けになります。
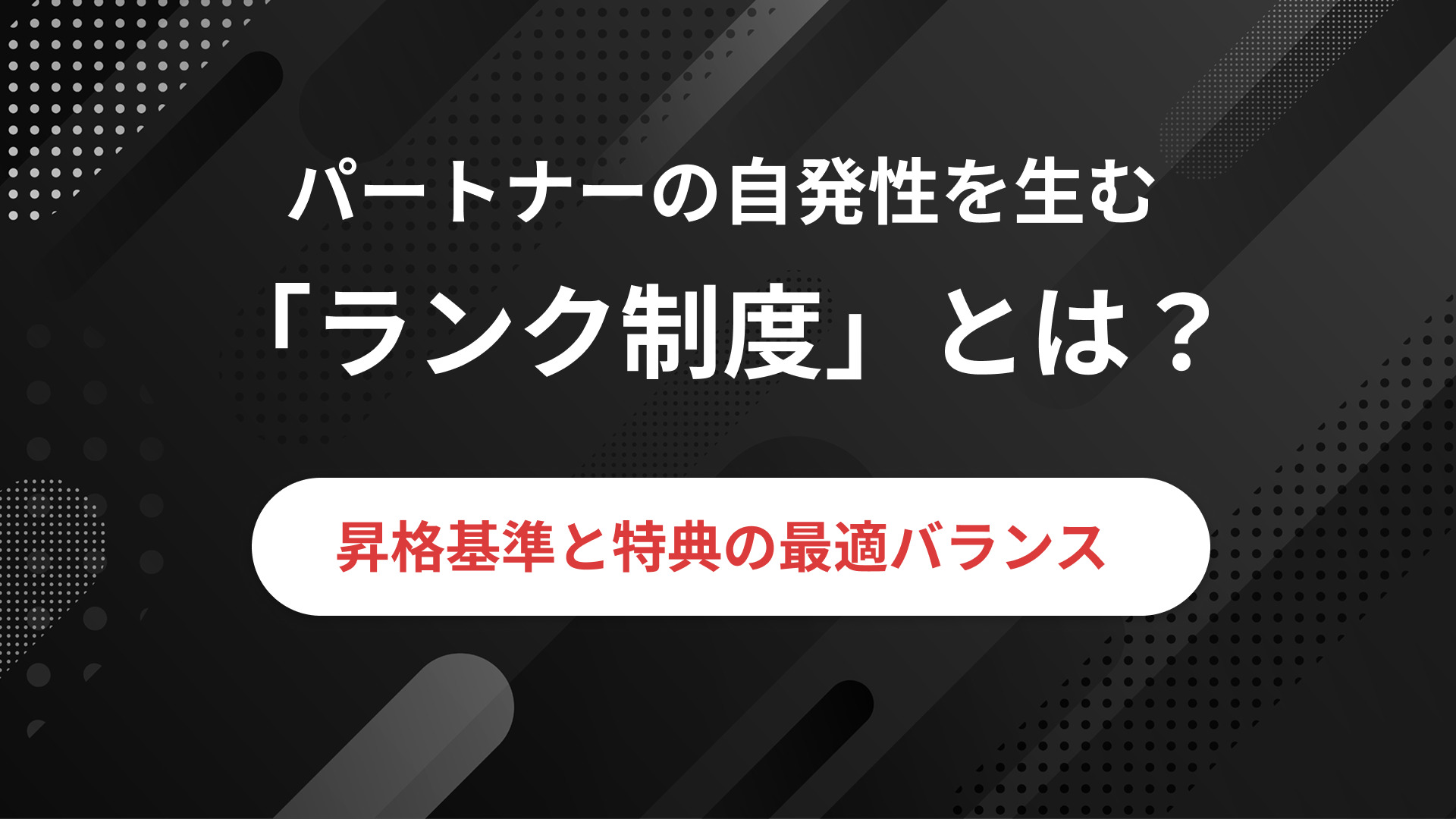
表彰やギフティングで感謝と注目を伝える
ここまで仕組み面での設計について触れてきましたが、最終的には人の感情をどう動かすかも重要です。心理学の研究でも、人は感謝や承認を受けることで有能感が高まり、行動を継続しやすくなると示されています。
そのため、数字で評価するだけでなく、表彰や称賛を通じて“貢献を可視化する場”を用意することが欠かせません。例えば、月間MVPの表彰や、貢献度に応じたインセンティブや記念品の贈呈などです。
HubSpotでは、年に一度、「インパクトアワード」としてグローバルおよび各地域で最もHubSpotを販売したパートナーを表彰しています。さらに、解約率の低さやウェブサイト構築での貢献など、販売以外の価値を創出したパートナーも表彰されます。また、新規参入から1年半以内のパートナーを対象とした「ルーキー・オブ・ザ・イヤー」枠も設けられており、多様な観点での称賛が行われています。
また、成功事例を社内に展開し、他社のパートナーへ共有することも有効です。さらに、成果が出る前の小さな取り組みに対しても賞賛を伝えることで、「見てもらえている」という感覚が生まれ、信頼関係の強化につながります。
リテンションは、契約して終わりではなく、協業を一緒に育てていく関係を築けるかどうかが問われるフェーズです。継続的に動き続けてもらうための仕組みを備えているかどうかが、パートナービジネス全体の成功を大きく左右します。
パートナーが動く仕組みを、明日から設計しよう
本稿で述べてきた通り、パートナーが動かないのは、意欲や能力の問題ではなく、パートナーに動いてもらう仕組みが整っていないことが原因です。「お願いします営業」から抜け出すために、最適なパートナープログラムを戦略的に設計することが必要不可欠です。
最後に「明日からできる最初の一歩」を紹介します。
1. 稼働中のパートナーにヒアリングする
まずは、パートナーが動かない原因を把握することが出発点です。
「導入フローが複雑で顧客に案内しづらい」「提案書の作成に時間がかかる」といった声は、仕組みの改善ポイントを見つける手がかりになります。
2. パートナーと「協業のメリット」を議論してみる
「なぜこの協業に取り組むのか」をあらためてパートナーと対話し、両者の戦略や期待値をすり合わせる場を持ちましょう。協業の意義が共有できれば、その後の伴走や支援も意味のあるものに変わります。
3. 成果報酬の前倒しを試してみる
案件登録時点や初回提案の段階など、成果の一歩手前でインセンティブを設ける工夫も有効です。必ずしも大規模な報酬設計である必要はなく、例えば「案件登録でポイントを付与する」「初回商談で販促資料やリード情報を優先的に提供する」といった小さな仕組みでも十分に効果があります。
「提案したらすぐに何か返ってくる」という仕組みがあるだけで、パートナーにとっての初動のハードルは大きく下がります。
4. まず1社に対して伴走支援をやってみる
商談同席、提案支援、定例レビューなど、本気で一社と向き合うサポートを実施してみることです。そこから得られた学びは、他のパートナーにも転用できる再現性のある知見になります。
小さく試し、改善し、仕組みにしていく。これこそが「動くパートナー」を増やすための現実的な一歩です。一から仕組みを作ることは、短期的には工数を要するかもしれません。しかし中長期的には、最も工数を減らし、最も成果を上げる投資になります。ぜひ、明日から実践してみてください。