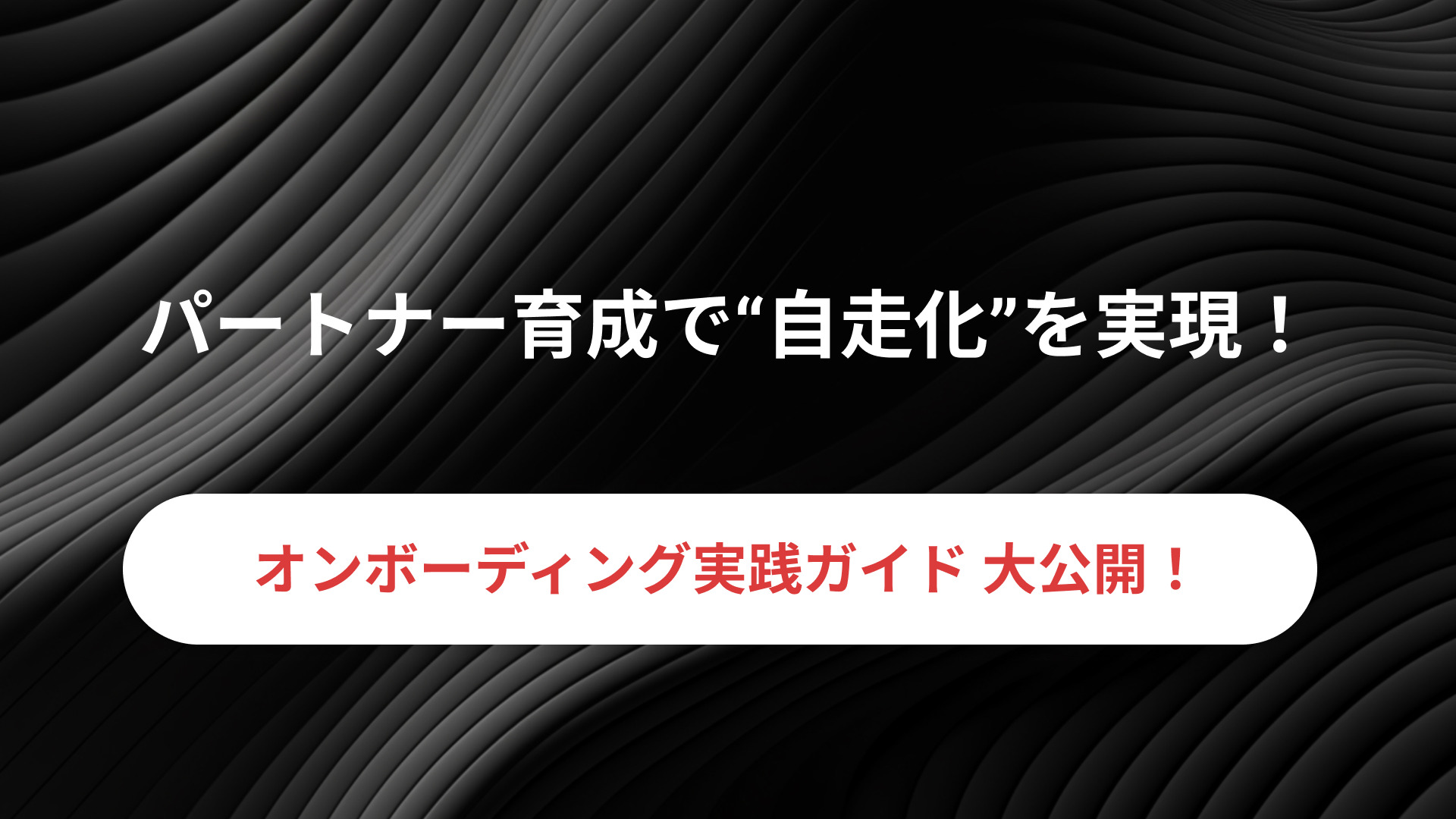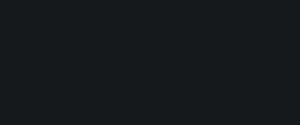目次
契約した販売パートナーが思うように動いてくれない ── そんな悩みを抱える企業は少なくありません。その原因として見落とされがちなのが、パートナーのオンボーディング不足です。単に契約を結んだだけでは、パートナーは自律的に提案活動を行ってくれるわけではありません。
パートナーが提案しない背景には複数の要因があります。
・競合商材を複数扱っており優先度が上がらない
・顧客課題と価値訴求の結びつきが弱い
・現場で使える資料・トークがない
ただし、すべてに共通する基盤はプロダクト理解の不足です。理解度が低いほど提案は後回しになり、機会損失が増えます。だからこそ、パートナー企業の担当者に、提案に必要な知識やスキルを積極的に身につけてもらうためのパートナーオンボーディング設計が重要になります。
本稿では、パートナーにとって負担なく学べ、かつ自主的な提案活動へ直結するオンボーディング設計の具体的な進め方を解説します。
オンボーディング不足が招く機能不全─解決の鍵は体系的な育成
実際にオンボーディングコンテンツ不足は、現場で見過ごされがちな課題です。
多くの企業がパートナー戦略に苦戦している背景には、パートナー側への情報提供や学習機会の欠如が潜んでいます。パートナー企業の営業担当者は平均して複数社の競合製品・サービスを扱っており、自社商材だけに注力させるのは容易ではありません。パートナー自身がすべての商品知識を独力で習得し、提案資料まで用意するのは現実的ではなく、ベンダー側で必要なコンテンツを整備しなければ自社製品を積極的に売ってもらえないのが実情です。その結果、「支援コンテンツがない=育たない=パートナーが動かない、成果が出ない」という悪循環に陥っているケースが多くあります。
また、十分なオンボーディングが行われていないパートナーは「とりあえず案件だけ取ってくる営業」になってしまう傾向があるため、低品質なリード(見込み客)ばかりが増えてしまい顧客継続や追加受注につながらず解約が多発するという 質の問題 も発生します。PLAINER株式会社の阿久津氏は、「パートナービジネスにおいても、その場の売上だけでなくLTV(顧客生涯価値)も重視すべきだ」と語ります。受注後にすぐ利用が止まるケースを避けるためにも、育成段階で適切な期待値調整を行い、プロダクト理解を十分に担保することが欠かせないと強調しています。
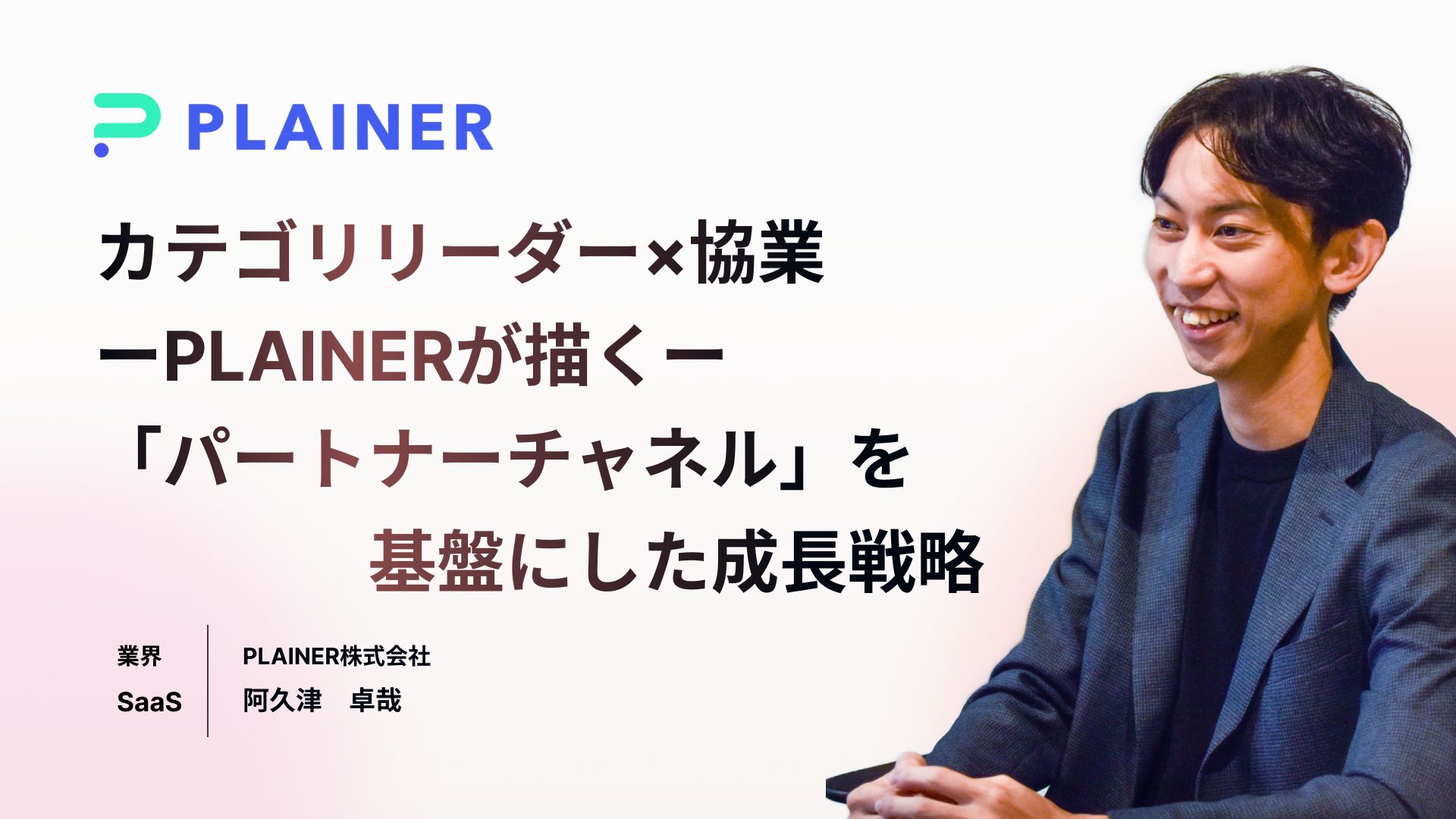
このように、これらの課題を解消するためには、パートナーを単なる数合わせの「外部営業」と見なすのではなく、自社の成長をともに担うビジネスパートナーとして位置づけ、体系的なオンボーディングによって戦力化していく視点が欠かせません。
パートナー育成 施策大全大公開!
まずは動画コンテンツとWebテストから始めてみよう
パートナーに対してオンボーディングを実施したいが、何から手を付ければいいのか分からない場合は、まず最小構成のコンテンツから着手するのがおすすめです。
具体的には、動画コンテンツとWebテストの組み合わせが効果的です。
動画は自社製品やサービスの概要、デモ、提案トーク例などを分かりやすく解説するコンテンツとして、パートナーの学習に最適です。現代において、スマートフォンでの動画視聴は一般的となっているため、スマートフォンで学べる環境を提供することが、自社のサービス営業で忙しい担当者にも効果的です。
動画やその他の資料に加えて、Webテスト(e-ラーニングコンテンツ)を組み合わせることで、学習効果は格段に高まります。オンラインテストで習熟度を測定することで、パートナー各担当者がどの程度理解できているかを「見える化」できます。
例えば、製品基礎編の動画を視聴した後にWebテストで理解度を確認する、といった流れです。テストによって習熟度を定量的に把握できるため、後述する改善サイクルに役立てることができます。
このように動画とWebテストというシンプルな組み合わせから始めることで 、大掛かりな研修会に頼らないオンボーディングの実施が可能です。まずは短尺の動画コンテンツ数本と簡単な確認テストからスタートし、パートナー育成の第一歩を踏み出しましょう。「小さく始めて、徐々に拡大」という方針が、無理なく持続的に運用するコツです。
オンボーディング推進に必要な、設計・運用・改善の具体的なアクション
パートナーオンボーディングを効果的に進めるには、以下の3つのステップで設計→運用→改善のサイクルを回すことが重要です。
STEP1:受講者ごとオンボーディングプログラムを設計する
まずは、パートナー企業の中で育成すべき対象を明確にし、それぞれに最適化したプログラムを設計します。パートナーと言っても、紹介だけを行うのか、商談を担当する営業なのか、導入後のCSも行うのかで必要な知識は異なります。研修を企画する際は、受講者の役割やスキル水準に応じてカリキュラムを作り分けましょう。例えば商談を行う営業向けには製品の価値提案や競合比較、セールストークの研修を用意し、提供するといった具合です。対象別にコンテンツを用意することで、「自分に関係ある内容だけ学べる」という状態を作り、学習効率と実務適用度を高めます。
STEP2:学習と実践のサイクルを整える
つづいて、設計したプログラムを実際に運用し、学習から実践(案件創出)につなげる流れを構築します。具体的には、前述の動画学習とWebテストを組み合わせて担当者の知識習得度を測定し、測定できたデータをもとにパートナープログラムを改善していきます。インプット→テスト→実践を一連のプロセスとして設計することで、パートナーは学んだことをすぐ実践に移しやすくなり、パートナー企業の中の売れる人を増やしていきます。オンボーディングと成果を結びつける仕組みを整えることで、パートナー企業内で研修を受けっぱなしにさせず、学習→実践のサイクルを回せるようになります。
STEP3:データを見ながら運用を改善する
プログラムを開始したら、定期的にデータを収集・分析して効果測定と改善を行います。オンライン研修なら、動画の視聴履歴やテストの得点といったデータが自動で蓄積されます。これらの学習データをもとに、パートナー全体の習熟度やアクティブ率を把握しましょう。例えば「全受講者のうち何割がテスト合格したか」「動画を途中離脱する人が多いコンテンツはどれか」「研修を終えた担当者はどれくらい案件獲得につながっているか」といった指標を参考に、コンテンツ内容や形式の見直し、追加研修の企画、あるいは個別フォローアップを実施します。特に成績優秀なパートナー担当者(キーマン)の行動は貴重なヒントになります。キーマンへのヒアリングを通してサービス理解資料やトークスクリプト集、商談動画といったコンテンツを作成し、全パートナーに展開することも効果的です。逆にテスト結果が芳しくないローパフォーマーには追加講習や個別研修の機会を設けるなど、データドリブンでオンボーディングプログラムを改善していくことが必要になります。
オンボーディングを効率化するPRMツール「PartnerProp」
上記のステップを効率良く回すには、ツールの活用によるDX化は欠かせません。パートナープロップではパートナーの管理ができるPRM(Partner Relationship Management)ツールに学習管理(ポータル・eラーニング)の機能が組み込まれています。パートナー企業ごとの案件情報を個人単位で一元管理できるだけでなく、ポータルによる動画や資料などの提要やEラーニング機能による問題の提供も可能になります。
また、各担当者の動画視聴履歴や自社製品に関する知識レベルを数値で可視化できます。
このような情報をもとに、どの動画が理解度が上がるのか、誰が売れる状態にあるのかを理解でき、オンボーディングコンテンツをアップデートしていくことができます。

このようにパートナープロップを活用することで、簡単に学習管理を行いつつ、オンボーディングプロセスを見える化することで、効率的かつ戦略的にパートナーをオンボーディングすることができます。また、ツールを活用すれば多数のパートナーを体系的に育成・管理でき、人的リソースが限られる場合でもパートナープログラムをスケールさせることができます。
PartnerPropのサービス資料をダウンロード↓

成果を最大化するためのポイントと落とし穴
オンボーディングをパートナービジネスの成功に繋げるために、押さえておきたいポイントと陥りやすい落とし穴をいくつか紹介します。
成果を最大化するためのポイント
研修を「認定制度・ランク制度・インセンティブ設計」と連動させ、仕組み化すること
パートナーが動画視聴やテストを「やりっぱなし」にせず継続的な動機付けとするには、パートナープログラムの制度と結び付けることが重要です。例えば研修修了者に公式の認定資格を発行し、パートナーランク(シルバー・ゴールド等)の要件に据える方法があります。前述のように、研修完了を成果報酬(コミッション)やリード配分の条件にすることも効果的です。このように学習→認定→報酬のサイクルをプログラムに組み込むことで、パートナー企業内で自主的に学習する文化を醸成し、オンボーディングを成果につなげる“仕組み”ができます。
パートナーランク制度は以下の記事で詳細に書いております。
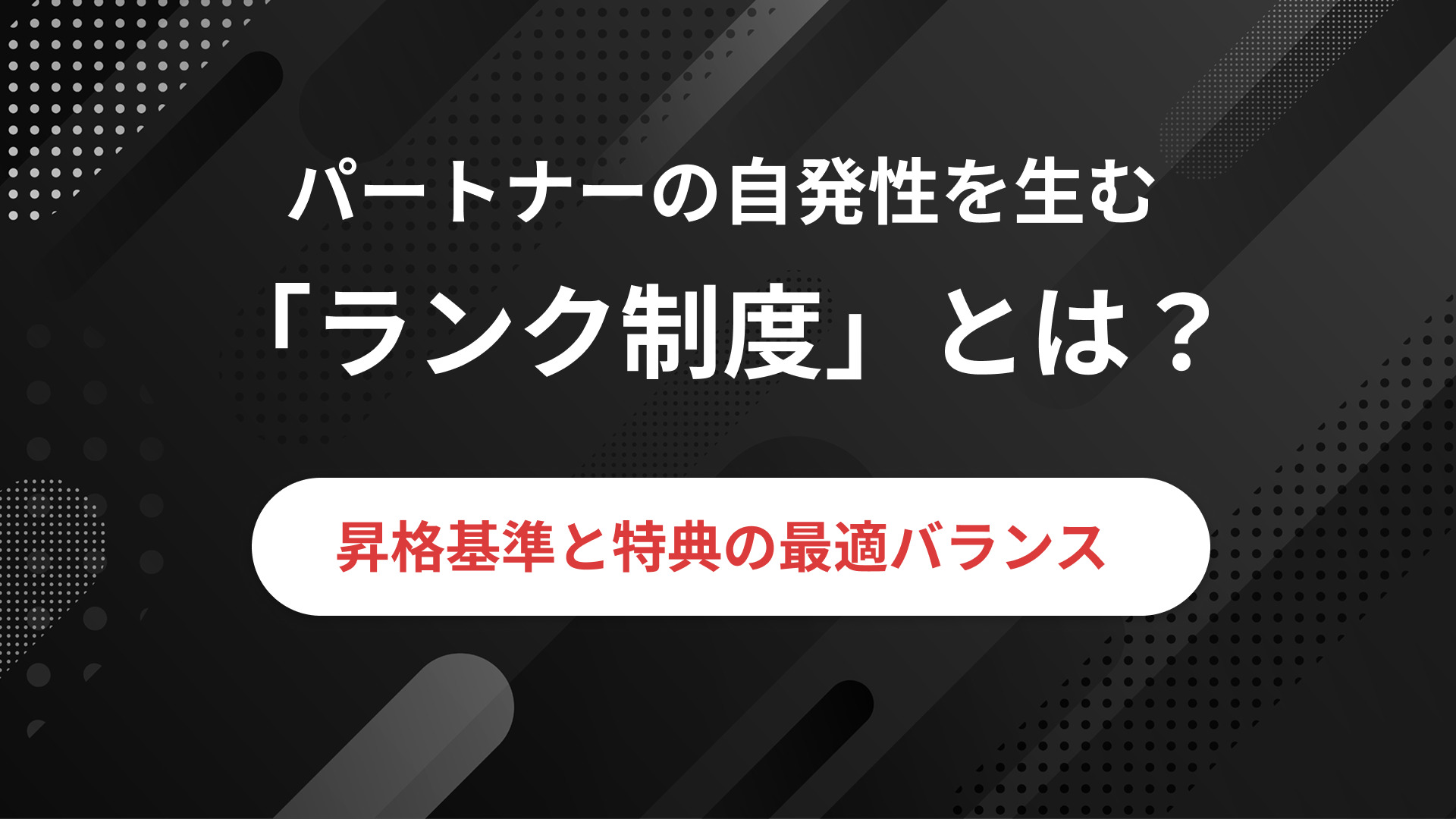
パートナー育成のミスに繋がる落とし穴
最初に気合いを入れすぎると失敗することがある
パートナー育成に取り組み始める際に陥りがちなのが、最初から完璧を目指して大規模かつ厳格な研修制度を構築しようとすることです。しかし、初期に力を入れすぎると運用が破綻するリスクがあります。コンテンツを詰め込みすぎた結果パートナーが消化不良を起こしたり、受講必須項目を増やしすぎて途中離脱を招いたり、自社の担当者側も運営に手が回らなくなることがあります。最初は小さく始めて徐々に拡大・改良していく方が、パートナーの受け入れも良く長続きします。「完璧より着手」を合言葉に、まず走り出し、後から改善するくらいの姿勢が丁度よいでしょう。
オンボーディングしただけで満足しない。動画研修の受講後の設計が重要
パートナー向け研修は、受講させて終わりではなく、受講後の行動変容や成果創出まで設計して初めて価値を発揮します。研修直後が最も知識が定着しているタイミングですので、その間に具体的なアクションにつなげる工夫が必要です。
以上の詳細は以下の記事に書いております。
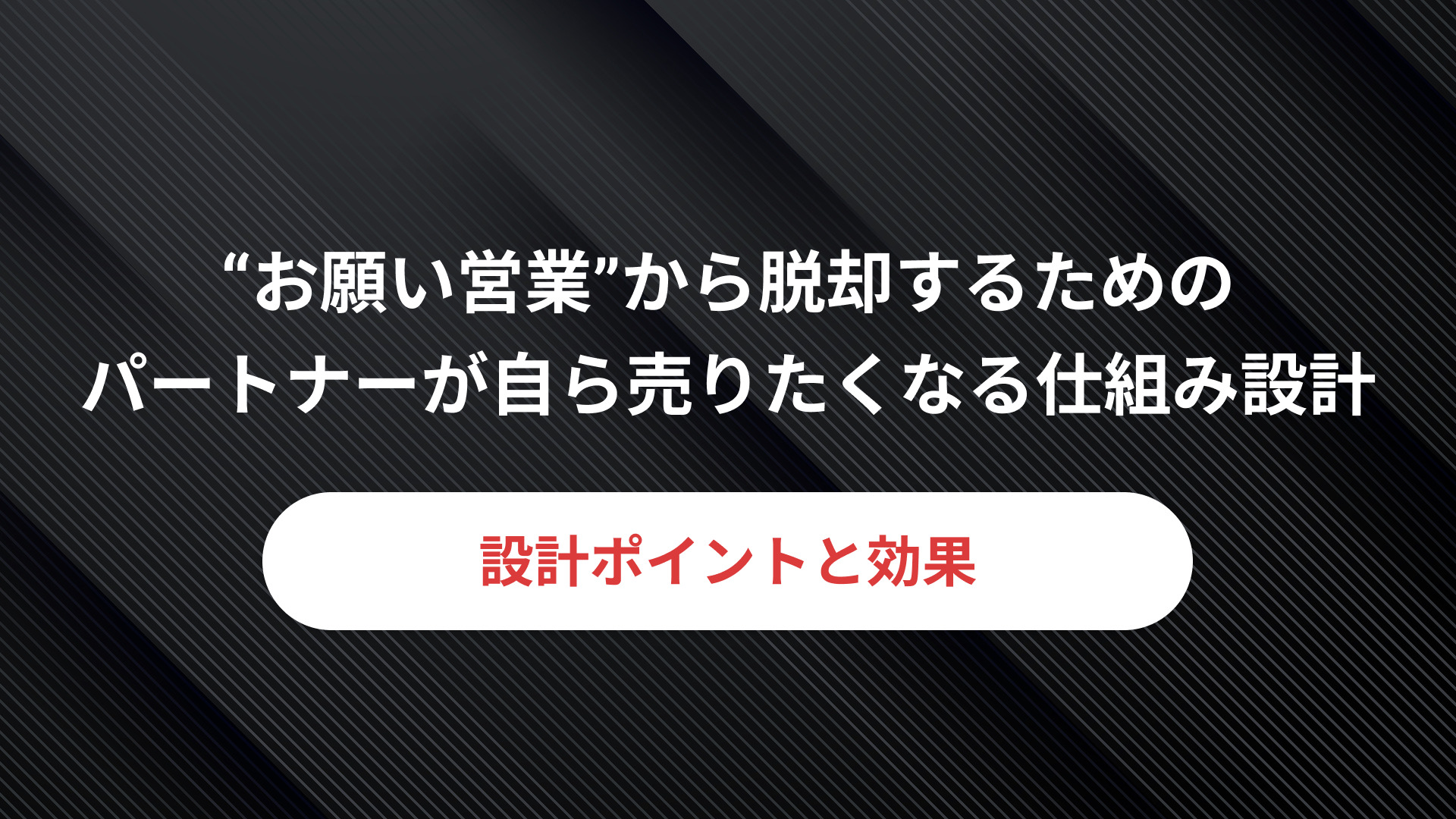
オンボーディングのPDCAサイクルを止めない。データを活用して質を高める
パートナー向けのオンボーディングは一度作って終わりではなく、常にPDCAサイクルを回し、改善し続ける姿勢が必要です。製品がアップデートするたびにオンボーディングコンテンツもアップデートが必要ですし、最初に作ったコンテンツが万能とも限りません。研修の受講率や合格率、受講者が担当した案件の成約率など、関連するデータを定期的に確認することが重要です。合格率の低い設問や視聴完了率の低い動画など、数値の低い箇所に対しては、原因を分析してコンテンツの改善につなげます。逆に成果が上がっているパートナーの成功要因を抽出し、他のパートナーにも共有することで全体の底上げを図ることもできます。このようにデータに基づいてオンボーディングプログラムをアップデートし続けることで、パートナー育成の質を高め、ひいてはパートナー経由の売上拡大につなげることができるのです。
まずは動画とテストから始め、改善するためのデータを積み上げよう
パートナー育成において何より重要なのは、まず始めてみることです。
完璧な制度設計や大ボリュームの教材を用意するのに時間をかけるより、小さくても良いので早期にプログラムを開始し、実際のパートナーの反応や学習データを集める方が得策です。蓄積された受講データやテスト結果は、次の施策改善の貴重な材料となります。最初は動画コンテンツ1本と簡単なテスト1つでも構いません。それを実際にパートナー数社に試してもらい、フィードバックを得ながら徐々にコンテンツを充実させていくことが大事です。完成度よりも「スタートを切ること」に価値があるというマインドで取り組みましょう。
もう一つ忘れてはならないのは、パートナーオンボーディング設計はパートナーとの信頼構築そのものだという点です。パートナー企業にとって、有用な知識やスキルを提供してくれるメーカーは非常に頼もしい存在です。「このメーカーと組めば自社も成長できる」とパートナーに思ってもらえれば、関係性は強固になります。育成を通じて得た知識や成功体験はパートナーの財産となり、貴社に対する熱烈なファンや心強い協力者へと育っていくでしょう。そうした信頼関係の醸成が、長期的なパートナー経由ビジネスの拡大には欠かせません。
最後に強調したいのは、パートナーが育てば、売上はあとからついてくるということです。短期的な数字だけを追いかけてパートナーを急かすのではなく、まずはパートナー企業の成長にコミットしましょう。パートナーの事業が成長すれば、自社の事業も自ずと成長していくものです。教育・育成に裏打ちされた強いパートナーほど、自社製品・サービスを自発的かつ継続的に提案してくれる頼もしい存在はありません。今まさに、「育成なしでは売れない時代」に突入しています。この流れに乗り遅れないよう、できるところからパートナー育成をスタートし、データを味方につけてプログラムを磨き込んでいきましょう。小さく始めてコツコツ積み上げた先に、きっと大きな成果が現れます。