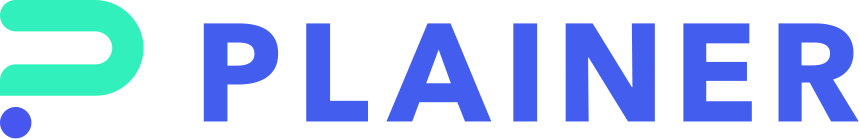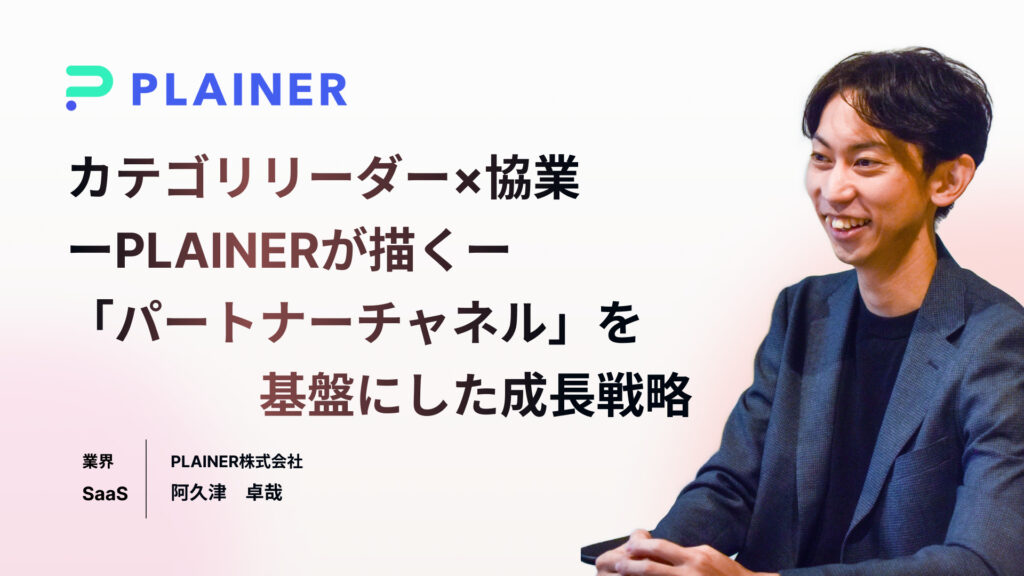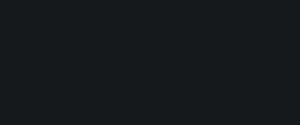目次
深い協業を基盤に据えたパートナービジネス
──貴社の事業内容について教えてください。
弊社は、ソフトウェアにおけるデモプラットフォーム「PLAINER」を提供しています。具体的には、ソフトウェアプロダクトの購買から導入、さらには利用促進に至るまでのプロセスにおいて、ユーザーを支援する「ソフトウェアイネーブルメントプラットフォーム」として機能することを目指しています。現在の仕組みでは、対象となるプロダクトのHTMLやCSSのコードをコピーし、本番環境と同じものを複製できます。これにより、ユーザーは実際のプロダクトと変わらない体験を手軽に試すことが可能になります。
日本のソフトウェア導入の現場では、ベンダーが優位でバイヤーが不利になる構造が根強く存在しています。そのため、検討段階で自社に合ったプロダクトが分からない、導入してみたものの自社のオペレーションに合わず、すぐに解約してしまうといった無駄なコストが生じる事例が少なくありません。その結果、「ソフトウェアは難しい」「導入しても失敗するかもしれない」という苦手意識や抵抗感が広がり、積極的な導入姿勢が社会に浸透していない状況です。私たちは「PLAINER」を通して、そのような課題を解消し、本来のソフトウェアプロダクトの価値を正しく理解していただくことを目指しています。
──貴社はどのような組織で営業活動を行っているのでしょうか。
弊社の正社員は全体で15名ほどで、ビジネスサイドとエンジニアサイドがおおよそ半数ずつを占めています。営業活動に関しては、現時点では直販が中心です。リード獲得のチャネルとしては、展示会のようなオフラインイベントやウェブセミナーを中心に活用しており、主要な集客経路になっています。
──現状のパートナービジネスの取り組み状況について教えてください。
現時点では、販売パートナーはほとんど存在していません。その一方で、私たちが注力しているのは「デモを通じたソフトウェアの事前体験の重要性」をSaaS企業を中心に広めるための協業です。
具体的には、展示会を主催する企業とアライアンスを組み、出展するSaaS企業に対して無償でPLAINERを利用していただく取り組みを行っています。そこで実際にデモを体験いただいた企業が、展示会をきっかけとして本契約へと進むケースも出てきています。
また、比較サイトと協業し、サイト上のおすすめ欄に各プロダクトのデモを掲載していただく施策も進めています。サービス資料とプロダクトデモをご覧いただくことで、商談化率の向上に繋がっています。
こうした取り組みを通じて、販売パートナーがまだ少ない段階にありながらも、深い協業を活用したパートナービジネスの基盤づくりを進めています。
──販売パートナーや紹介パートナーへの着手は、いつ頃を目指しているのでしょうか。
現在はアライアンスパートナーが中心ですが、一年以内に販売パートナーや紹介パートナーにも着手しようと考えています。その間に、まずはPLAINERというプロダクトの売り方や、カスタマーサクセス(CS)側での活用方法における再現性を確立し、誰でも売れる状態を現メンバーで作り上げることを重視しています。
具体的には、商談の場で顧客からいただいたフィードバックを現場メンバーから集約し、それをもとに「プロダクトをどのように提案すればよいのか」「どのように活用できるか」といったナレッジを蓄積していきます。こうした知見がなければ、パートナーに販売を任せることは難しいと考えています。だからこそ、今の私たちが取り組むべき重要課題として、ナレッジ基盤の整備に注力しているのです。

自社だけでは辿り着けない新たな市場へ
──協業を基盤にパートナービジネスを進めているとのことですが、その狙いは何でしょうか
私たちが提供している「ソフトウェアイネーブルメントプラットフォーム」というカテゴリーは、日本国内では現在PLAINERしか存在していません。そのため、このカテゴリーにおけるリーダーであり続けるためには、直販体制だけに依存するのでは限界があると考えています。
また、新たなカテゴリーや市場を形成していくにあたっては、パートナーを巻き込みながら広げていくことが不可欠です。まだ市場が十分に存在しない中でどのように開拓していくかを考えるとき、どれだけ多くの共感を持っていただける企業やパートナーを見つけられるかが極めて重要だと捉えています。
──現状の直販体制に感じている限界や、今後起こりうる課題感にはどのようなものがありますか。
SaaS事業では、ターゲットとなる企業との接点はどうしても限られてしまいます。現状は直販だけでも一定の成果を上げられていますが、5年後、10年後を見据えると、必ずより幅広い企業にアプローチしていく必要があると考えています。
私たちはこのカテゴリーを切り拓く立場にある以上、自ら市場を開拓し、より多くの企業にデモ体験を届けていく必要があります。その広がりを実現するためには、直販だけではなく、パートナーとともに市場を広げていくことが不可欠だと考えています。
──貴社におけるパートナービジネスの位置づけについて教えてください。
現段階でのパートナービジネスは、トップラインを直接伸ばすための販売チャネルという位置づけではありません。むしろ、市場をどのように形成し、その仕組みを作り上げていくかを目的とした取り組みとして位置付けています。
現在、PLAINERをご導入いただいているのは主にB向けのSaaS企業です。今後はこれを広げ、業種特化型のVertical SaaSや消費者向けのC向けSaaS、さらにはSIerといった領域も対象になっていくと考えています。しかし、現状ではリソースが十分ではないため、これらの領域には一部関わっているものの、本格的に深掘りできていない状況です。
だからこそ、パートナーと連携し、自分たちだけでは携わりきれていない領域も含めて新しい市場を切り開き、課題を共有しながらプロダクトを進化させていくことが重要だと考えています。
創業期だからこそ挑む、パートナービジネスの真価
──創業期であるにもかかわらず、なぜ「今」パートナービジネスに手をつける必要があると考えたのでしょうか。
現在、私たちの主要なターゲットはBtoB向けのSaaS企業ですが、それ以外にもC向けのSaaSなど含めて多様な領域にニーズが存在します。今のうちに、そうした広い領域からどれだけ要望を吸い上げ、プロダクトに反映できるかが、今後の成長において非常に重要です。
もちろん、後からプロダクトを改良していくことも可能ですが、現段階から全体のロードマップと結びつけて取り組むことで、より強いプロダクトを築くことができます。そのために「今」動き出すことが必要だと判断しました。さらに、パートナーを介することで、自分たちだけでは深掘りしきれていない顧客層の課題を掘り起こすことができるのです。
ーパートナーから課題を特定して、プロダクトを強化していくというのは大事な考え方ですね。
中長期的なプロダクトのロードマップや、私たちが目指す世界観を実現していく上でも、そうした課題の発見は不可欠です。「この方向性で本当に正しいのか」「別のアプローチがより適しているのではないか」といった視点を取り入れることで、プロダクト戦略をより精緻に磨き上げることができます。
その結果、営業戦略の方向性や、どの領域を優先的に攻めていくかという判断、さらには採用戦略にも影響を与えていきます。だからこそ今のうちから、パートナーを介して広い領域からのニーズを拾い集め、それをプロダクトに反映させていくことが重要だと考えています。
パートナーをどう選び、どう育てるか。PLAINERが描く実践戦略
──パートナー開拓はどのように実施しているのでしょうか。
パートナーの選定は非常に重要だと考えています。なぜなら、どの企業と組むかによってPLAINERのブランディングそのものにも大きな影響が及ぶからです。そのため、展示会を主催するような大きなパートナーと協業することは特に重視しています。
一方で、単に規模の大きさだけでなく、「協業することでシナジー効果が生まれるか」「将来的なビジョンが一致しているか」といった観点も重要です。こうした点まで丁寧に考慮しながら、協業先を選定するようにしています。
パートナーセグメントについては以下をご覧ください。
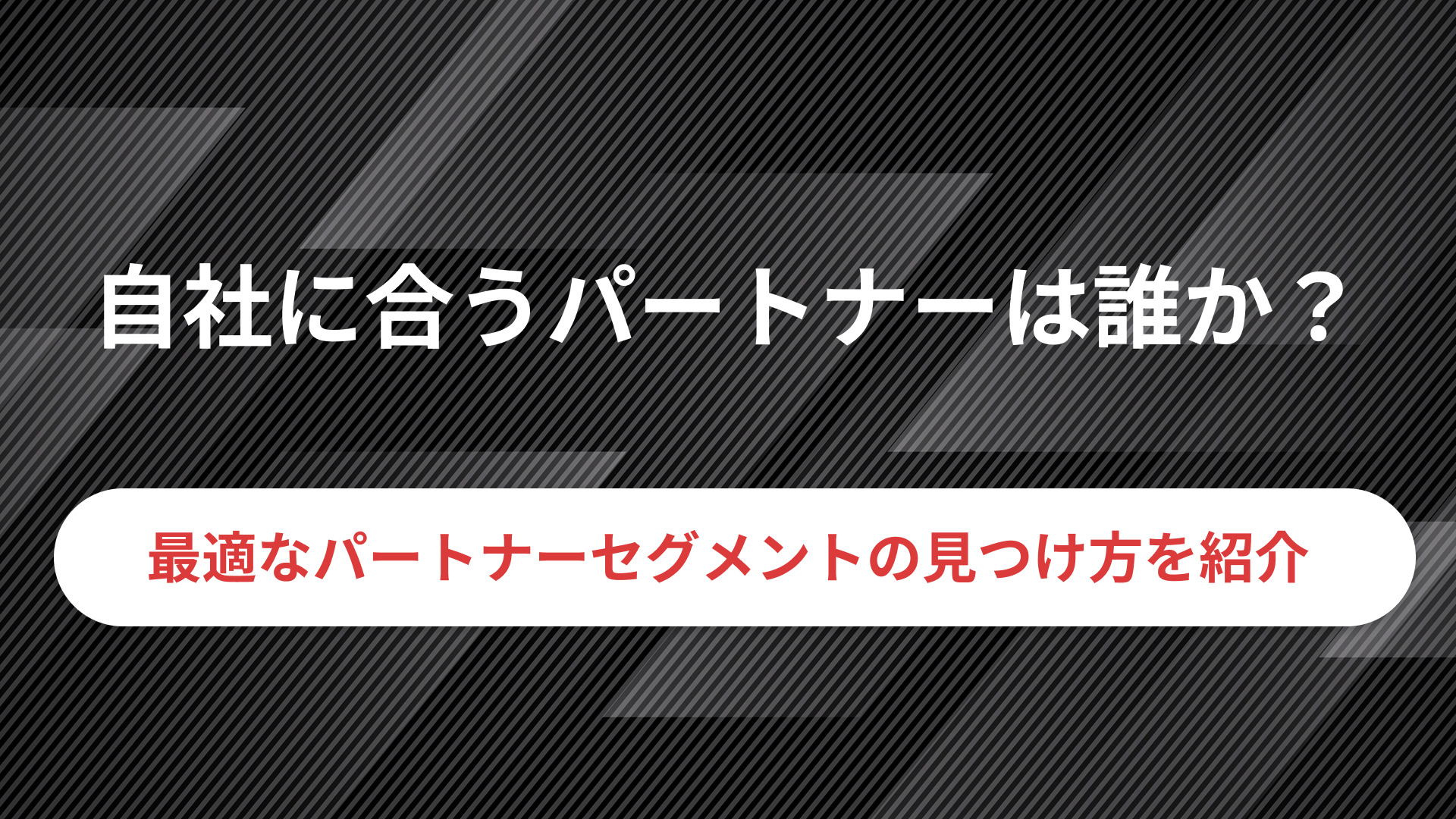
──パートナーの育成については、どのように取り組んでいきたいですか。
パートナーの育成は非常に重要だと考えています。実際にやり取りをしているご担当者には私たちのプロダクトに共感していただけていますが、その先にいる営業担当者や店舗スタッフにまでどのように理解を浸透させるかが課題です。プロダクト自体が難しい側面もあるため、勉強会などを通じてしっかりと育成を行っていきたいと考えています。
また、SaaS業界では「受注したものの1年も経たずに利用が止まってしまう」というケースが少なくありません。そうしたことを避けるためにも、パートナー育成の段階で適切な期待値調整を行い、プロダクトに対する理解度を十分に担保することが重要だと考えています。
さらに、パートナー育成はPLAINERならではの強みを発揮できる領域でもあります。パートナーは、複数のサービスを扱う中で、プロダクトの価値を十分に説明することが難しい場面も少なくありません。そうした状況においても、PLAINERを活用すれば、誰でもトップパフォーマーと同じクオリティのデモを容易に展開することができます。
育成については以下をご覧ください。
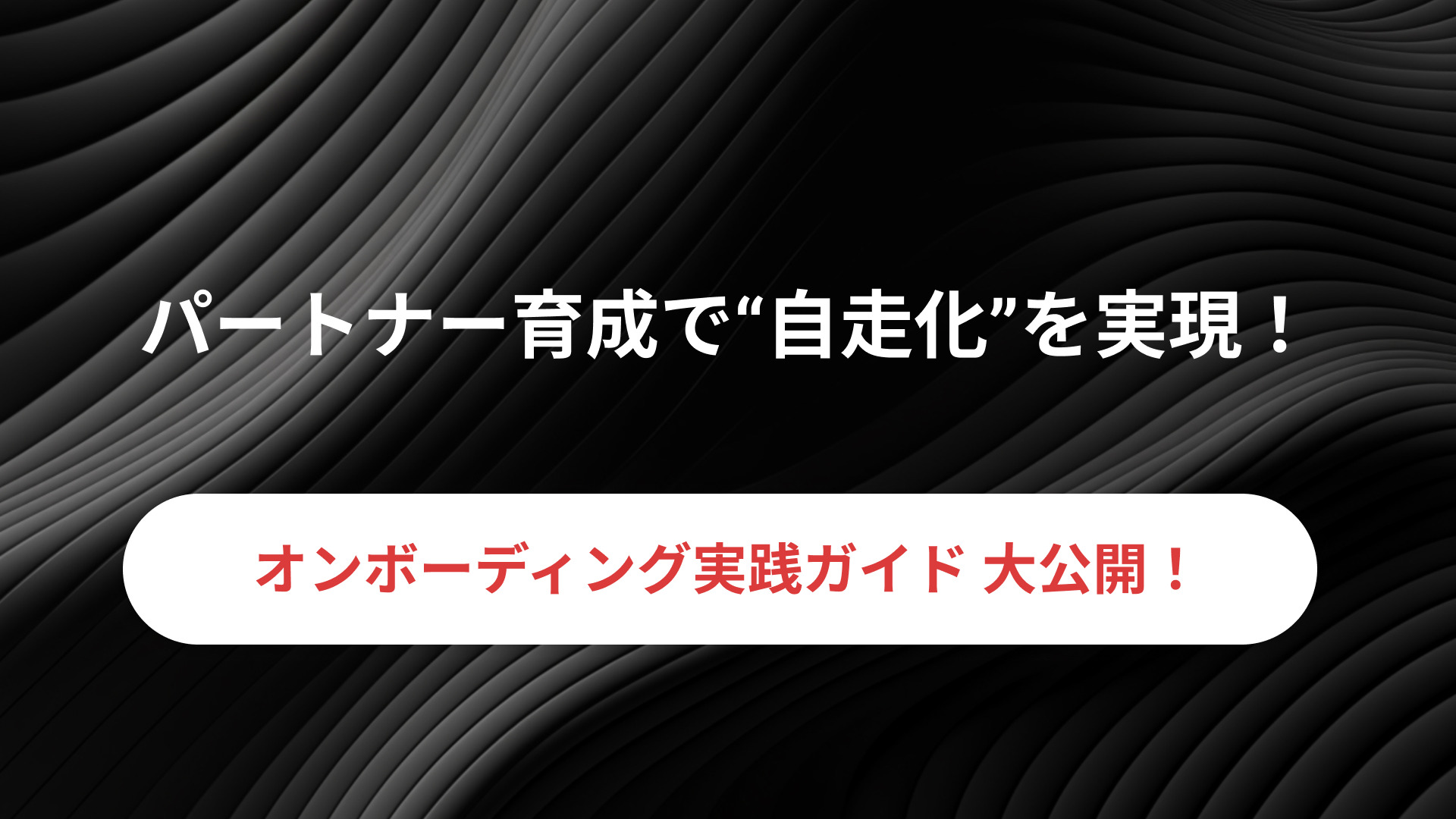
──1年後を見据える中で、描いているパートナープログラムの理想像はありますか。
私たちは「パートナーマーケティング」という考え方を重視しています。現状では、個々のパートナーごとにしっかりとマーケティングを行うことを意識していますが、今後パートナープログラムを設計していく際にも、この思想を基盤に据えて取り組んでいきたいと考えています。
手数料の設計やパートナーランク制度といった仕組みは後づけで整備していく予定です。あくまで土台にあるのはパートナーマーケティングであり、この思想を社内にも浸透させることが重要だと認識しています。
具体的には、11月ごろからパートナープログラムの設計により積極的に取り組み始め、将来的にパートナーとともに成長していける仕組みを作り上げたいと考えています。

パートナーとともにデモ体験の文化を広げ、誰もがソフトウェアを活用できる未来へ
──パートナービジネスについての今後の展望について教えてください。
今後取り組んでいきたいことの一つは、ナレッジを体系化し、共有するための土台を作ることです。現状では自社製品の売り方が個人のスキルや経験に依存している部分があるため、それを型化してナレッジを蓄積し、誰でも再現できる形に整えることを目指しています。そして、その知見をパートナーにも共有できるようにすることで、一貫性のある提案を可能にしていきたいと考えています。
もう一つは、パートナー開拓の基盤づくりです。私たちがデモを通じて実現したい世界観や、デモが購買行動に与える影響について、社内外の誰もが自信を持って語れる状態をつくりたいと思っています。海外ではすでにデモ体験を重視する文化が根づいていますが、日本ではまだ十分に浸透していません。だからこそ、「デモが顧客体験をどう変えるのか」をパートナーとともに発信し、共通の価値観として広げていくことを目指しています。
──貴社が作りたい世界観について教えてください。
私たちが描く世界観は、大きく分けて「ソフトウェアの購買活動における使われ方」と「導入後の活用」の2つの側面にあります。
まず購買の場面についてです。例えば家を借りるときには、必ず複数の物件を内覧し、価格やメリットを吟味した上で契約を決めます。車も同じです。にもかかわらず、ソフトウェアだけは同じように事前体験を重ねて比較することができないのはなぜだろうか、と感じています。実際、海外では当たり前に行われているのに、日本ではまだ十分に浸透していません。その背景には、日本特有の終身雇用制や組織の稟議プロセスが影響している部分もあります。そのなかで、将来的には「稟議を上げる際には、PDFの資料とPLAINERのデモが必ずセットになっていなければならない」ような状態を当たり前にしたいと考えています。
次に導入後の活用です。PLAINERを通じて「プロダクトをどれだけ使いやすくできるか」という点に力を入れていきたいと思っています。具体的には、PLAINERがプロダクトの使い方をすべてガイドしてくれるような仕組みを実現したいと考えます。海外では一社が導入しているSaaSの数は20前後にのぼりますが、日本はまだ非常に少ないのが現状です。その理由には、操作性の複雑さやユーザーのリテラシー不足といった要因があります。私たちは、PLAINERを通じてその障壁を解消し、誰もがソフトウェアをスムーズに使いこなせる環境を整えていきたいと考えています。
日本の労働環境には属人化などの課題が根強く残っており、これは今後10年、20年で急速に変わるものではないかもしれません。だからこそ、弊社やそのパートナーとともにデモプラットフォームによる導入体験や導入後活用の在り方を開拓し、こうした状況を改善していくことが非常に重要だと考えています。
その先に実現したいのは、「ソフトウェア界のドラえもん」のような存在です。のび太くんが困ったときにドラえもんに相談すれば適切なひみつ道具が返ってくるように、ユーザーがソフトウェアについてPLAINERに相談すれば「御社にはこのプロダクトが合います」「このプロダクトはこう使えば効果的です」といった具体的な支援が必ず返ってくる。そうした存在となることを通じて、まだ多くの人にとってハードルの高いソフトウェアやデジタル化を、誰もが自然に活用できる世界を実現していきたいと考えています。
ー本日はありがとうございました。
PLAINERのサービスサイト、採用サイトは以下にありますので、ぜひご覧ください。
<PLAINERサービスサイト>
https://service.plainer.co.jp/
<PLAINER採用サイト>
https://service.plainer.co.jp/recruit